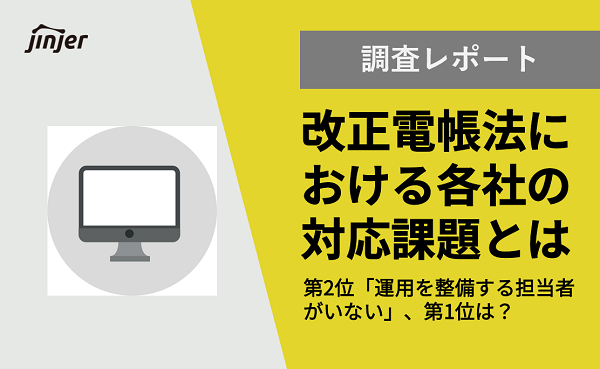電子帳簿保存法改正の変更点や目的、メリットをわかりやすく解説
更新日: 2024.5.29
公開日: 2020.11.9
OHSUGI

電子帳簿保存法はこれまでに何度か改正されています。2021年にも改正がおこなわれ、2022年の1月より改正内容が施行されました。
電子帳簿保存法とは領収書や帳簿を電子データで保存する際に重要な法律です。
こちらの記事では、2022年に施行された電子帳簿保存法改正の変更点と、改正の背景や目的、対応するべき事柄についてわかりやすく解説していきます。
2024年1月より、電子取引における電子データ保存の義務化に対する宥恕期間の廃止といった大きな変更点も含まれていますので、ここでしっかり押さえておきましょう。
【調査レポート】2022年「改正電子帳簿保存法」に向けた各社の現状とは?
一部猶予が与えられた改正電子帳簿保存法ですが、各社の対応状況はいかがなのでしょうか。
そこで電子帳簿保存法に対応したシステムを提供するjinjer株式会社では「改正電子帳簿保存法対応に向けた課題」に関する実態調査を実施いたしました。
調査レポートには、
・各企業の電帳法対応への危機感
・電帳法に対応できていない理由
・電帳法の対応を予定している時期
・電帳法対応するための予算の有無について
などなど電子帳簿保存法対応に関する各社の現状が示されています。
「各社の電帳法の対応状況が知りたい」「いつから電帳法に対応しようか悩んでいる」というご担当者様はぜひご覧ください。
目次
1. 2022年1月に施行された法改正の変更点とその背景


今回の改正では、保存をおこなう際の要件が抜本的に見直され、電子帳簿保存法がより利用しやすい内容へと変更になりました。ここでは、2021年に改正され、2022年1月1日より施行されている電子帳簿保存法の主な改正内容を解説していきます。
1-1. スキャナ保存・電子取引でのタイムスタンプの要件緩和
領収書などの書類のスキャナ保存や電子取引において、画像データの修正や削除などの変更した履歴が残るシステムを利用している場合は、タイムスタンプが実質不要になるということです。
また、タイムスタンプの付与期限が、従来は3営業日内であったのに対し、付与期限が各書類の受け取りから最長2ヵ月まで、おおむね7営業日以内に延長されました。
また、書類の入力に関して、入力の期限が書類を受け入れてから2ヶ月以内の入力に統一されます。
関連記事:電子帳簿保存法のタイムスタンプって何?最新の要件や改正内容を解説
関連記事:電子帳簿保存法のタイムスタンプ、費用ってどのくらい?導入手順も解説
関連記事:電子帳簿保存法の「3日以内ルール」を守れば領収書は電子化できるの?要件を解説
1-2. 帳簿の電子保存の事前申請が不要になった
改正電子帳簿保存法の施行前までは、運用開始の3ヶ月前までに所轄の税務署へ申請し、承認を得た後でなければ、帳簿や書類の電子保存をおこなえませんでした。
2022年1月1日以降、保存規定を守った方法で保存をおこなえば、事前の申請や承認を受けずとも、帳簿や書類の電子保存が可能になりました。
関連記事:改正電子帳簿保存法における事前申請が不要になるのはいつから?改正点や保存要件も解説
1-3. 「取引年月日・取引金額・取引先名」の3点のみに検索要件が緩和
これまでの検索要件では、さまざまな項目での検索が可能な状態を求められていましたが、今後は「取引年月日・取引金額・取引先名称」の最低3項目に緩和されます。
このように、電子帳簿保存法に対応した経費精算システムを使用することで、これまでかかっていた手間や煩雑な管理を必要とせずに電子帳簿保存法へ対応できるように法律の内容が変化しています。
1-4. 電子取引における電子保存の義務化
2022年の電子帳簿保存法改正では、初の電子保存を一部義務化する改正がおこなわれています。
電子取引において授受した注文書や契約書、送り状、領収書、見積書などの取引情報は、紙に出力せずに、電子データのまま保存することが義務付けられました。
ただし、この電子保存の義務化に関しては、対応が間に合わない事業者に配慮し、2023年12月末までは宥恕措置(猶予期間)が設けられています。
また、2024年1月以降の電子保存に関しては宥恕措置に変わり、猶予措置が整備されました。
猶予措置は「2023年12月まで宥恕措置を適用して保存していた方」に限定して案内されているため、2024年以降に切り替えることは難しいでしょう。
今のうちに対応方法を定めておく必要があります。
関連記事:電子帳簿保存法に猶予が設けられた理由は?改正内容や対応策を解説
関連記事:電子帳簿保存法で注文書を電子化するための方法と要件は?]
1-5. 適正事務処理要件の廃止
スキャナ保存に関しては、事務処理を2名以上でおこなう相互牽制のほか、適切に事務処理されているかの定期的な検査の実施、不備があった際に対処する再発防止体制などの適正事務処理要件が設けられていました。
しかし、2022年1月以降に施行された法改正によって、これらの適正事務処理要件は廃止となり、スキャナ保存が以前よりも運用しやすくなっています。
1-6. 要件を緩和する目的と背景
電子帳簿保存法はスキャン保存制度による納税者の負担軽減や従業員の生産性向上などを目的としていましたが、対応するハードルが高いことが大きな問題となっていました。
電子保存をおこなうために事前申請が必要なことや、定期検査時の原本の確認といった煩雑な作業は引き続き必要だったため、思うように普及しなかったのです。
これらの実態を改善し、より利用率を向上するために今回の改正がおこなわれました。
関連記事:電子帳簿保存法の要件を総まとめ|2022年施行内容も解説
2. 2024年から新たな変更点あり
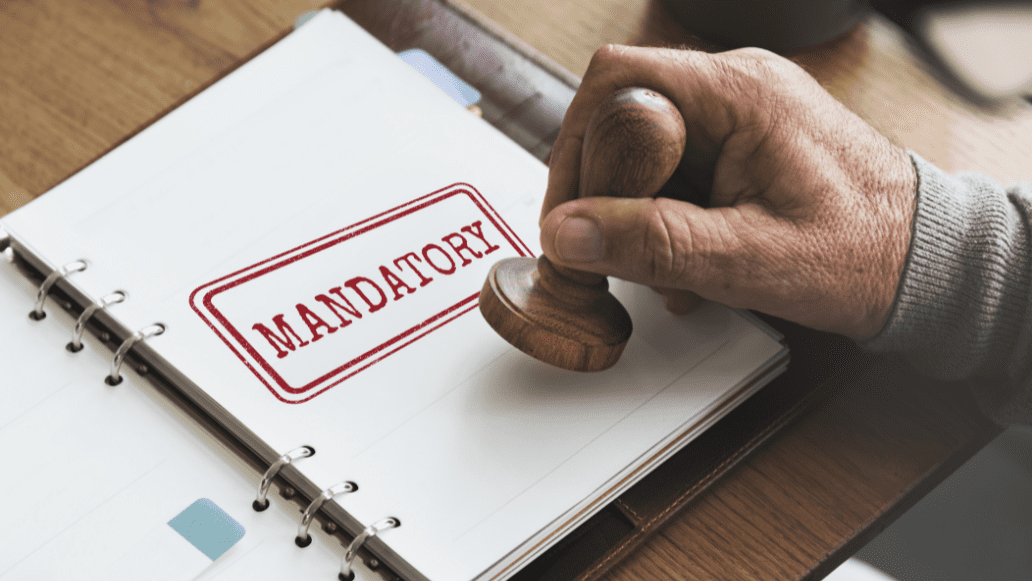
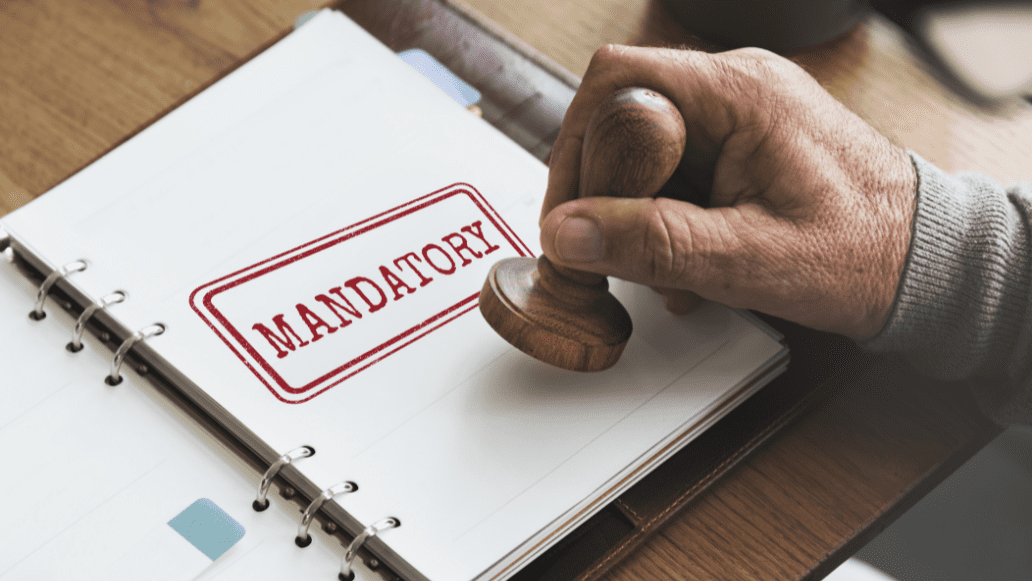
電子帳簿保存法は2023年にも改正されています。現在の保存要件だけでなく、2024年以降の変更点も押さえておく必要があるでしょう。
ここでは、2024年1月1日から施行される変更点について解説します。
2-1. 電子帳簿保存の保存要件における変更点
電子帳簿の保存要件における変更点は「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の範囲見直しです。
2022年1月の法改正により電子帳簿の保存要件が、以下の2つに分けられました。
- 優良な電子帳簿保存
- その他の電子帳簿保存
優良な電子帳簿の要件を満たす場合は、別途申請することで、「過少申告加算税の軽減措置」や「青色申告の特別控除額の増加」といった恩恵を受けることができるようになっています。
しかし、その要件に「全ての青色申告に必要な帳簿」と記載されていたため、具体的にどの帳簿を電子化すれば良いかわかりませんでした。
今回の改正で「必要な帳簿」が指定されたため、具体的にどの帳簿を電子化すれば良いかが明確となっています。
2-2. スキャナ保存要件における変更点
スキャナ保存要件においては3つの変更点があります。それぞれ解説するので、確認しましょう。
2-2-1. 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要になる
現行法では、解像度や階調の下限制限を守るだけでなく、その情報を保存しなければならない、とされています。
2024年1月以降にスキャナ保存する国税関係書類に関しては、この「解像度」や「階調」、「大きさ」に関する情報を保存することは不要となるため、より電子保存しやすくなるといえるでしょう。
ただし、解像度や階調の下限制限がなくなるわけではないため、注意が必要です。
2-2-2. 入力者等情報の確認要件が不要
入力者等情報の確認要件とは、「スキャナ保存をおこなった本人」または「その監督責任者」の情報を保存・確認できることです。
これらの要件も2024年1月1日以降にスキャナ保存するものに関しては不要となります。
※電子取引データ保存も同様です。
2-2-3. 「帳簿との相互関連性の確保が必要な書類」が重要書類に限定
現時点では、スキャナ保存した国税関係書類は全て、帳簿との相互関連性を持たせなければなりません。
2024年以降は、「お金や物の流れに直結しない書類(一般書類)」は相互関連性を持たせていなくても、電子保存できるようになります。
2-3. 電子取引データ保存要件における変更点
電子取引データ保存要件についても変更点があります。それぞれ確認しましょう。
2-3-1. 検索機能の全てを不要とする措置の対象者の見直し
現在の法律では、2年前の売上高が1,000万円以下の事業者は「ダウンロードの求め」に応じることができる場合に限り、検索機能の要件を満たしてなくとも電子データ保存を認められています。
今回の見直しで、この対象範囲が5,000万円以下の事業者に拡大されました。
また、売上高が5,000万円以上であっても、「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている事業者」についても、検索機能の要件が不要となります。
2-3-2. 宥恕措置の廃止
現行法でも、電子取引データ保存は「電子データのまま保存しなければならない」という決まりがあります。
しかし、2022年1月の施行日に間に合わない企業も多いことから、2023年12月末まで宥恕措置を設けて「相当の理由があると税務署長が認めた場合に限り、電子保存していなくても構わない」とされているのです。
今回、この宥恕措置の期間を延長せず、廃止することが発表されました。
2-3-3. 猶予措置の整備
先述のとおり、宥恕措置は廃止されるものの、新たに猶予措置を設けることが決まっています。
猶予措置は無期限で適用されるかわりに、「相当の理由があると税務署長が認めた場合」に加えて、「電子取引データのダウンロードの求めに応じること」「電子取引データを印刷した書面を提示・提出できること」が条件に追加されているので、注意しましょう。
3. 電子帳簿保存法とは
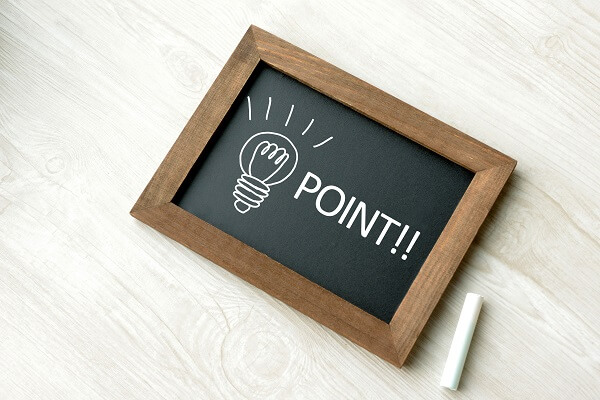
今回の電子帳簿保存法の改正だけでなく、電子帳簿保存法はこれまで何度か改正されてきました。
電子帳簿保存法全体を理解しておくことは大切になるので、ここで理解しておきましょう。
関連記事:参考記事:【2023年版】電子帳簿保存法とは?概要と改正内容をわかりやすく解説
3-1. 電子帳簿保存法とこれまでの経緯
電子帳簿保存法とは、帳簿や領収書などの処理にかかる負担軽減のために電子データでの保存を認めた法律です。
電子帳簿保存法は1998年に制定された法律で、その後何度か改正がおこなわれてきました。
例えば、2005年にはスキャンしたデータで書類を保管するも可能になりました。
続いて2015年には、保存要件が緩和され企業が電子データの保存に取り組みやすい改正がおこなわれています。
その後2016年に大幅な要件の緩和がおこなわれ、経費精算の手間が大幅に削減できるようになりました。
スマートフォンやデジカメで撮影した領収書であっても、電子保存が可能になったのです。
これは企業にとって非常に大きな変化でした。
また、2020年10月の改正では、タイムスタンプ付与の要件緩和、データの改変が出来ない、もしくは変更履歴が残るタイムスタンプを用いている場合に関しては一部領収書が不要になるといった変化もありました。
このように電子帳簿保存法は改正を繰り返して、企業がより簡単に電子データの保存に取り組めるようになってきました。
3-2. 電子帳簿保存法の対象となる文書
電子帳簿保存法の対象となる文書は、以下のとおり3種類あります。
- 国税関連帳簿:仕訳帳、総勘定元帳、売掛・買掛帳、経費帳など
- 国税関連書類:損益計算書、貸借対照表 、請求書、⾒積書、領収書、納品書など
- 電子取引書類:請求書、見積書、領収書、納品書など
国税関連帳簿、国税関連書類については、自己のパソコンで作成したものは紙に出力せずに保存します。なお、国税関連書類のうち取引関連の書類はスキャナでの電子保存が可能です。電子取引書類に関しては、やり取りした電子データを保存します。
この3つの書類のうち、2024年1月以降に電子保存の完全義務化の対象となるのは、電子取引による文書です。
4. 電子帳簿保存法のメリット

電子帳簿保存法のメリットに関して別記事でも解説していますが、電子帳簿保存法にスムーズに対応するためにも、今一度確認しておきましょう。電子帳簿保存法のメリットは以下の通りです。
関連記事:電子帳簿保存法のメリットを簡単に理解したい!基礎知識やデメリットもわかりやすく解説
4-1. オフィスの省スペース化
日本では、法人は取引記録を帳簿につけ、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間にわたって保存することが義務づけられています。
なお、赤字経営で繰越欠損金が出た場合は、平成20年4月1日以後に修了した欠損金の生じた事業年度については9年間、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度については10年間にわたり、帳簿の保存が必要です。
国税帳簿書類は一般的にファイルやバインダーなどに綴じ、キャビネットなどで保管しますが、7年ないし10年もの間保管し続けるとなると書類の数は膨大になり、少なからずオフィスのスペースを占有してしまうでしょう。
しかし、帳簿書類を電子データ化すれば、紙で残す必要がなくなるため、オフィスの省スペース化を図ることができます。
4-2. 経理業務の効率化
大半の企業は帳簿書類を年度ごとに分けて保管しますが、たくさんある書類の中から目当ての一枚を探し出すのはかなりの手間と時間がかかるものです。
書類探しに手間取っていると、そのぶん他の作業が滞ってしまうため、業務効率を低下させる一因にもなり得ます。
その点、帳簿書類を電子データとして保存しておけば、検索機能を使って目当ての書類を簡単に探し出すことが可能です。
業務効率が上がれば、生産性アップにもつながり、売上や業績にも良い影響をもたらすでしょう。
また、紙の帳簿を閲覧するのはオフィス内に限られますが、帳簿書類を電子化してクラウド上に保管しておけば、場所や時間を問わず帳簿書類にアクセスできるようになります。
例えばスマホやタブレットなどを使って帳簿書類の電子データを呼び出せば、取引先や出張先からでも簡単に帳簿書類を閲覧することが可能です。
いちいちオフィスに戻る手間がなくなり、時間を効率よく使えるようになるところも電子帳簿保存法を適用する大きなメリットといえます。
4-3. コスト削減
紙の帳簿を作成するには、用紙のほか、印刷に使うインクも用意しなければなりません。
さらには、保管用としてファイルやバインダー、キャビネットなども購入する必要があり、保管が長期間に及ぶほど経費もかさむ傾向にあります。
帳簿書類を電子データとしてコンピュータに保存すれば、印刷や保管にかかるコストを大幅に節約できるため、経費削減につながります。
4-4. 環境問題への配慮
企業は自社の利潤を追求するだけでなく、消費者や投資家、さらには社会全体からの要求に対して責任を果たす姿勢を求められます。
これを企業の社会的責任(CSR)といい、昨今では企業イメージの向上や取引先との関係強化に欠かせない活動とされています。
CSR活動の種類は多岐に亘りますが、中でも代表的なものがエコ活動による環境問題への貢献です。
電子帳簿保存法の適用により、企業のペーパーレス化が進めば、貴重な紙資源を節約して省エネ・エコを推進することができます。
4-5. セキュリティの強化
帳簿書類はオフィス内のキャビネットなどに保管し、無人になる時はオフィス・キャビネットの双方を施錠して盗難に備えます。
ただ、鍵が物理的にこじ開けられてしまった場合、悪意ある第三者に帳簿書類を盗まれてしまうおそれがあります。
盗難だけでなく、オフィスレイアウトを変更する際や、引っ越しの際に書類を紛失してしまう可能性もゼロではありません。
帳簿書類を電子データ化し、クラウド上で保存したうえで閲覧制限を設ければ、第三者にデータを盗まれる心配がなく、セキュリティを強化できます。
クラウド上のデータはIDやパスワードを管理していれば、いつでも引き出すことができるので、引っ越しやレイアウト変更にともなう紛失のリスクも少なく、安心してデータを保管できるでしょう。
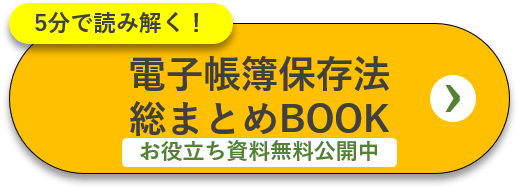
5. 電子帳簿保存での注意事項


今回の改正で電子帳簿保存法の要件が緩和さたものの、スキャナ保存の要件や保管期間で気をつけるべき点がいくつかあります。また、違反した際の罰則にも注意が必要です。
ここでは、それぞれの注意事項について詳しく解説します。
5-1. 電子データの保存要件(スキャナ保存)
スキャナ保存には下記の注意事項があるため確認しておきましょう。
- グレースケール(白黒)スキャンが認められるのは一般書類のみで重要書類はカラーでスキャンする必要がある
- 書類のサイズが大きい場合や複数ページにわたる場合など、一度にスキャンできない場合は複数回のスキャンが可能。原本を縮小コピーしたスキャンは認められないため注意が必要
関連記事:電子帳簿保存法におけるスキャナ保存について、要件や申請手順を解説
5-2. 帳簿や書類の保管期間
各帳簿や書類には保管期間があります。税法上では帳簿書類の保管期間は7年と定められているため、電子データも7年間保管するようにしましょう。
電子帳簿保存法の要件に従って電子データで保管している場合、原本については破棄しても問題ありません。
関連記事:電子帳簿保存法に対応後の税務調査で必要なものは?原本保管はしておくべき?
5-3. 違反するとペナルティがある
電子帳簿保存法も違反すると罰則があります。改正で導入が簡易化した一方で、不正行為に対するペナルティは強化されているため注意が必要です。
電子帳簿保存法に違反し帳簿の保管が適切でなかった場合や、スキャナ保存がおこなわれた国税関係書類の電子データに隠蔽や改ざんがあった場合は、申告の不備による重加算税がさらに10%加重される措置が整備されました。
また、帳簿の保管不備は会社法にも違反することになり、会社法第976条の定める所により100万円以下の過料が課される可能性もあります。
関連記事:電子帳簿保存法って違反したら罰則はあるの?リスクと要件を解説
6. 電子保存義務化に向けた準備と対策


2023年12月には、電子取引による電子データの保存義務化の宥恕期間が終了してしまいます。2024年1月からは、猶予期間が適用となっている企業を除き、電子取引による電子データの保存義務化に対応しなければなりません。
ここでは、電子保存に対応するためにしておくべき準備や対策について解説します。
6-1. データの保存方法や保存場所を決める
まずは、電子保存の対象となっている文書のうち、紙で保存されているものと電子化されているものをチェックします。その上で、それぞれ電子保存の要件を満たすために必要な準備を進めていきましょう。
電子保存をおこなうには、訂正や削除の事実が確認できる「真実性の確保」や、必要項目で検索・表示ができる「可視性の確保」など、保存方法の要件も確認しておくことが必要です。
また、保存場所についても決めておかなくてはいけません。部署によって保存場所が異なることが無いよう保存場所を統一化させ、万が一のデータ破損に備えてバックアップ体制の整備をしておくことも重要です。
電子帳簿保存法の理解を今一度整理しておきたい方は、電子帳簿保存法改正をわかりやすくまとめた「電子帳簿保存法総まとめBOOK」を用意していますので、ぜひそちらもご確認ください。
参考:2022年度(令和4年)改正版|5分で読み解く!電子帳簿保存法
6-2. 電子帳簿保存法に対応したシステム導入を検討する
上述のとおり、電子帳簿保存法は度重なる法改正によって、内容が幾度となく変更されています。そのため、常に最新の法改正に目を光らせておくことが必要です。
しかし、他の業務で多忙を極めていると、なかなか法改正にまで目が行き届かないのが実情でしょう。限られた人材でスムーズに電子化に対応するには、電子帳簿保存法に対応した経費精算システムの導入がおすすめです。
システムの中には法改正に自動対応したものもあるため、面倒なシステム設定の変更をおこなう必要もありません。またペーパーレス化によって、業務効率の向上も期待できます。
2024年1月以降の電子取引による電子データの保存義務化のタイミングに合わせて、システムの導入を検討してみるのも一つの手です。
7. 電子帳簿保存法改正のメリットを最大限活用しよう

今後多くの企業が、帳簿や書類を電子保存していく方向へシフトしていきます。
前回2020年の法改正によって、社内のペーパーレス化の促進や経理担当者の負担軽減、リモートワークの促進など、さまざまなメリットがもたらされました。
しかし、電子保存できる文書とスキャナ保存できる文書には違いがあったり、タイムスタンプに対しての従業員の理解が追い付いていなかったりと、不安がある方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、電子帳簿保存法の改正内容をまとめた無料の資料を配布しておりますので、改正のポイントを押さえて、電子帳簿保存法のメリットを最大限に活かしましょう。
2020年、2022年の電子帳簿保存法改正を
わかりやすく総まとめ!
1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。
しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律そのものの内容、対応の手順など理解しなければならないことは多いです。
「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
資料では
・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説
・2020年10月改正内容と2022年の最新内容のポイント
・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件
など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。
「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
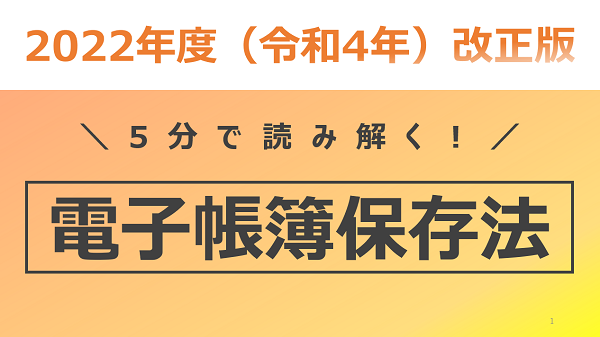
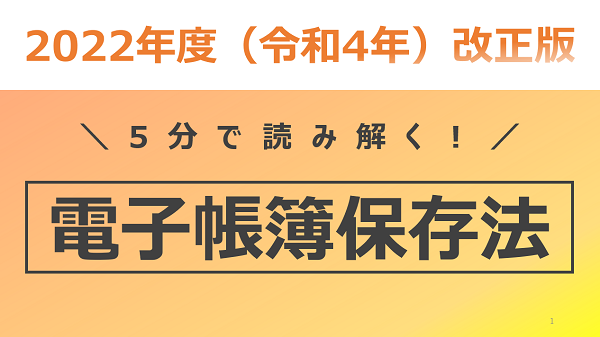
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04