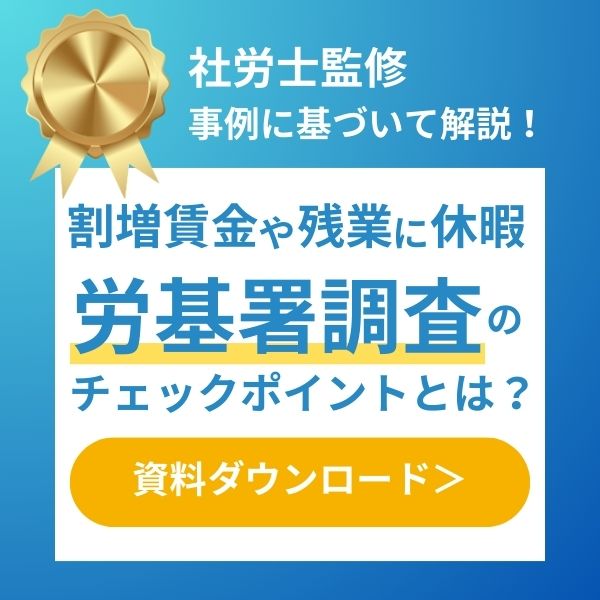労働時間管理で記録と実労働が乖離してしまう原因とその対処法
更新日: 2025.10.6 公開日: 2020.3.10 jinjer Blog 編集部

勤怠管理においてもっとも注意が必要なのが、従業員の実際の労働時間と、会社側の労働時間の記録の「乖離」です。2019年4月、働き方改革の進展にともない労働安全衛生法が改正され、ただ労働時間を計算するだけでなく、「客観的な記録」として保存・管理することが義務付けられました。
しかし、労働者の勤務時間と、タイムカードや日報などの記録に乖離が見られる事業所が少なくありません。労働者とのトラブルに発展し、裁判がおこなわれた事例もあるため、リスクを避けるためにも厳格な労働時間管理をおこなう必要があります。
この記事では、実態とデータの乖離が起きてしまう原因や、その対処法を解説します。
関連記事:労働時間について知らないとまずい基礎知識をおさらい!
目次
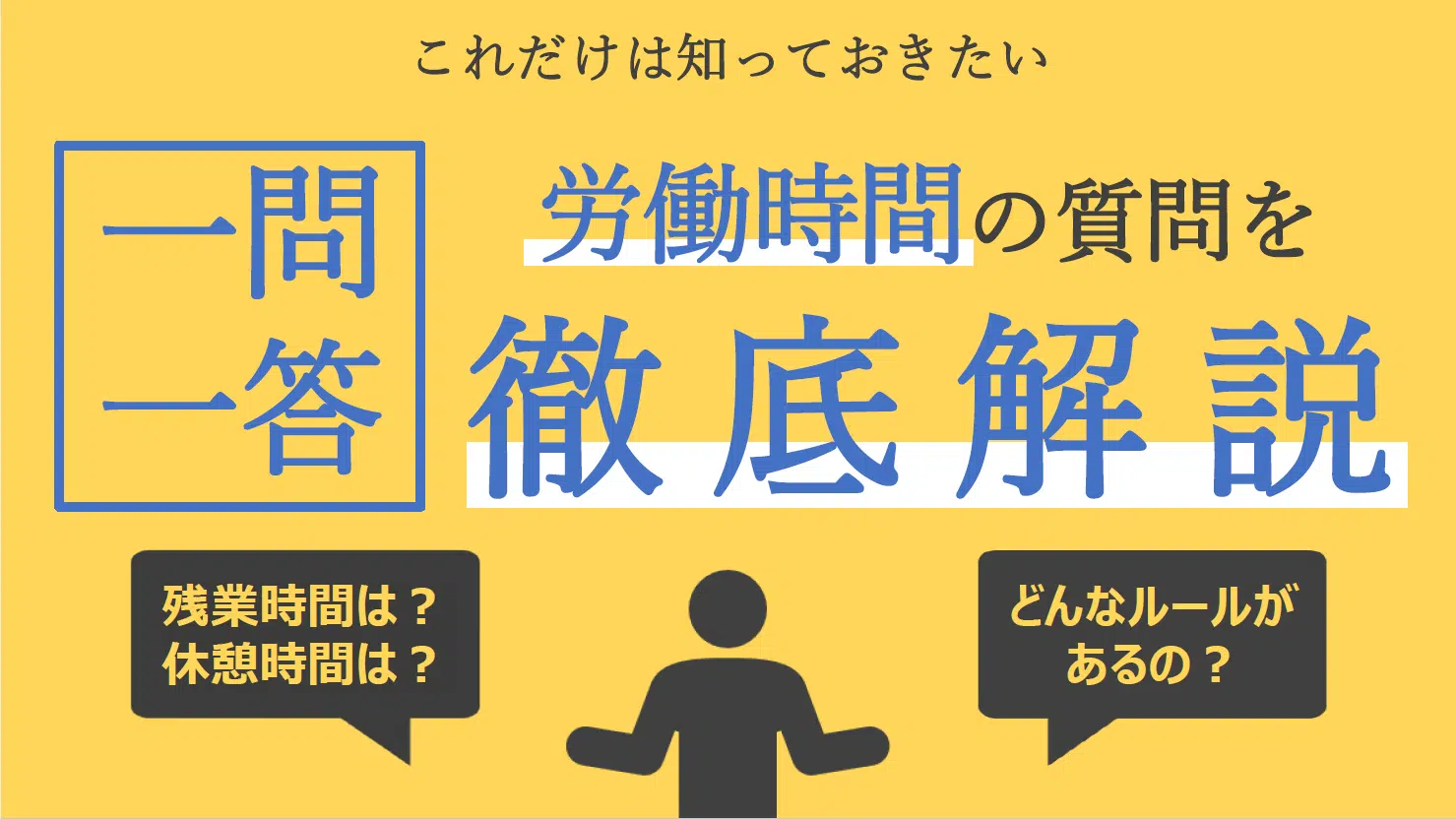
多様な働き方の導入や度重なる法改正により、労働時間管理はますます複雑になっています。
「この対応で本当に正しいのか?」という日々の不安は、コンプライアンス違反という「知らなかった」では済まされないリスクに直結します。
当サイトでは、労務管理の土台となる労働時間の知識をQ&A形式で解説した資料を無料配布しています。
◆この資料でわかること
- 曖昧になりがちな「勤務時間」と「労働時間」の明確な違い
- 年間労働時間の算出など、給与計算にも関わる重要知識
- トラブルを未然に防ぐための休憩時間の付与ルール
- 罰則リスクを回避するための正しい勤怠管理のポイント
労務リスクへの備えは、企業の信頼を守る第一歩です。自社の勤怠管理体制の見直しに役立ちますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 労働時間の乖離とは

労働時間を管理するうえで、しばしば実態とデータの乖離が生じます。例えば、タイムカードで労働時間を管理している場合、「従業員が勤務を終えた時間」と「タイムカードを打刻した時間」にはわずかな乖離があります。
労働時間の乖離とは、このような従業員の実労働時間とタイムカードに記された労働時間との差が開いている状態です。
2. 実際の労働時間と勤怠記録の結果が乖離する3つの原因

労働時間の乖離は企業や事業所によっては、かなりの開きがあるケースも存在します。労働時間の実態と記録が乖離してしまうのは、大きく分けて3つの原因があります。
2-1. 従業員によるタイムカードの不正打刻
労働時間が記録とずれる原因の1つが、従業員によるタイムカードなどの不正打刻です。タイムレコーダーを不正に操作したり、代理の人物に打刻してもらったりするなどして、「残業していないのにもかかわらず、実際よりも遅い退勤時刻に打刻する」「遅刻したのにもかかわらず、通常の始業時間に打刻する」といった不正がおこなわれることがあります。
厄介なのが、不正な打刻であっても、タイムカードの記録は労働時間の客観的な証拠となる点です。
実際、2000年におこなわれた残業代の未払いをめぐる裁判では、企業側の主張する労働時間ではなく、タイムカードの記録が認められ、支払いを命じられる結果となっています。
2-2. 手書きの日報などによる不正な自己申告
タイムカードと同様、手書きの日報や出勤簿のような自己申告制の労働時間管理方法も注意が必要です。報告する際に誤った数値を記入したり、悪意を持って虚偽の報告をおこなったり、不正な自己申告がなされるリスクがあります。
逆に企業側が労働者に圧力をかけ、残業時間や時間外労働時間を申告できる上限を設けるといった不正をおこない、労働基準監督署の調査が入った事例も存在します。
2-3. 定期的な実態調査をおこなっていない
タイムカードにせよ、手書きの日報にせよ、労働時間の実態と記録の乖離が起きるのは、企業側が定期的に「実態調査」をおこなっていないからです。とくに手書きの日報は労働時間の客観的な記録といえません。
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」でも、実態調査をおこなうことが推奨されています。具体的には、労働者への定期的なヒアリングのほか、入退館の記録、金庫の開閉記録、警備システムのログ、パソコンのログイン履歴といった「客観的な記録」を比較材料として使う方法があります。
ガイドラインでは「著しい乖離がある場合には実態調査を実施」とだけ示されており、調査が必要となる乖離時間の目安までは示されていませんが、一般的には30分の乖離を一つの目安としている所が多いようです。
参考:労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
3. 労働時間の乖離についての判例

従業員の実労働時間とタイムカードの打刻時間とで乖離があった場合、どちらが採用されるのでしょうか。過去の判例では直行直帰の届けがあるといった特別な事情がない限り、タイムカードに基づいて実労働時間を推定するとされています。
そのため、もし従業員が実際の業務は終わったのに関わらずオフィスに残り、帰り間際に打刻をした場合、タイムカードの打刻が労働時間として扱われることになります。
4. 労働時間の乖離が発生した場合の対処方法

労働時間の乖離が発生した場合、事実確認や原因を追求しなくてはいけません。乖離のある状態を放置することは、先にも述べたようなリスクが伴います。企業側は以下のような対処を講じて、早急に改善を図りましょう。
4-1. 自己申告による労働時間の乖離が発生した場合
自己申告制により、始業・終業時刻の確認及び記録をおこなう場合、実際の労働時間と従業員が申告した労働時間に乖離が発生する可能性があります。
しかし、実際の労働時間と従業員が申告した労働時間に乖離が発生していても、違法ではありません。
厚生労働省のガイドラインによると、「自己申告により企業が把握している労働時間と従業員の実際の労働時間が合致しているか、企業は必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正すること。」と記載されています。
特に、入退場記録やパソコンのアクティビティログなど、従業員が職場にいたことが分かるデータと従業員から申告された労働時間に著しく乖離がある場合には、実態調査を実施し、労働時間を修正する必要があります。
参考:労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
4-2. 「アクティビティログ」を積極的に活用する
労働時間の実態調査をおこなう際は、「アクティビティログ」を活用しましょう。アクティビティログとは、PCやスマホ、タブレットなどの操作履歴のことです。
パソコンのログイン、ログオフの記録はもちろん、チャットアプリやWeb会議ツールなどのソフトウェアの操作履歴も「アクティビティログ」です。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」でも、「パソコンの使用時間の記録等」は労働時間の客観的な記録として認められています。
アクティビティログを基礎として実態調査をおこなえば、タイムカードや手書きの日報における不正打刻・申告などを防止できます。
関連記事:タイムカードはもう不要?GPSで打刻できる勤怠管理システムとは
5. 労働時間管理で実際と記録が乖離するのを防ぐ2つの方法

労働時間管理において、事前に乖離を防ぐ仕組みを構築しておくことも必要です。ここでは、実態と記録が乖離するのを防ぐ2つの方法についてご紹介します。
5-1. 残業や時間外労働の「事前申請制度」を設ける
労働時間の実態と記録がとくに乖離しやすいのが、残業時間や時間外労働時間です。就業後は、その場に管理者がいないことが多く、従業員1人ひとりに目が行き届きません。
そこで、残業、休日出勤、深夜労働については、直属の上司の事前承認を必要とする仕組みを作りましょう。事前に許可した時間だけしか時間外労働が認められないため、実態との乖離が起きにくくなります。
5-2. 勤怠管理システムを使用して客観的な労働時間の把握をする
勤怠管理システムを導入することで労働時間の乖離を防止することができます。
勤怠管理システムとは、スマホやタブレットなどから打刻し、従業員の労働時間を集計・管理できるソフトウェアです。いつでもどこでも打刻できるため便利な一方、「誰が」「いつ」打刻したかが客観的な記録として残るため、実態と記録の乖離が起きにくくなっています。
さらに、スマホやタブレットのGPS機能を使った「GPS打刻」なら、位置情報を取得することができます。これにより、例えば「自宅にいるのにスマホで打刻し、出勤したかのように装う」といった不正を防止できるため、労働時間管理をより適正化できます。
このほかにも、勤怠管理システムには労働時間の自動集計など便利な機能が数多く備わっています。勤怠管理システムでなにができるかを知りたい方は、以下のリンクより勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページをご覧ください。
▶クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページを見る
6. 実際の労働時間と勤怠記録の乖離を防ぐために企業は3つの対策を

今回は、労働時間の実態と記録が乖離してしまう原因や、その対処法を解説しました。実態との乖離が生じる主な原因は、タイムカードや手書きの日報を悪用した不正です。
不正を防止するには、企業がアクティビティログなどを活用し、定期的な実態調査をおこなう必要があります。また、勤怠管理システムを導入すれば、打刻した人物や時間の客観的な記録が保存されるため、より正確な労働時間管理が可能です。
GPS打刻に対応したシステムなら、「誰が」「いつ」「どこで」打刻したかの3点がわかるため、実態と記録の乖離を防止できます。
関連記事:タイムカードはもう不要?GPSで打刻できる勤怠管理システムとは
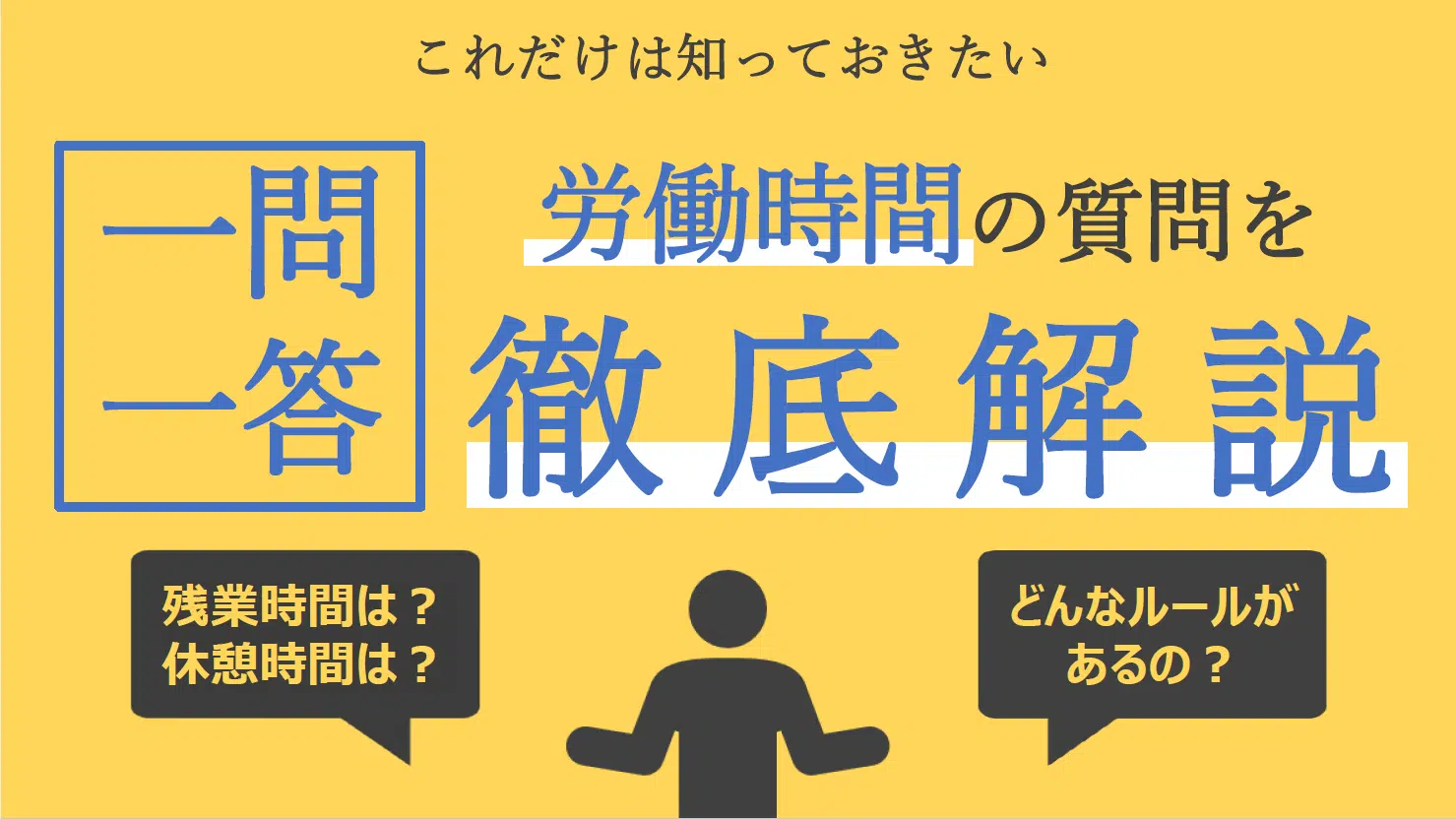
多様な働き方の導入や度重なる法改正により、労働時間管理はますます複雑になっています。
「この対応で本当に正しいのか?」という日々の不安は、コンプライアンス違反という「知らなかった」では済まされないリスクに直結します。
当サイトでは、労務管理の土台となる労働時間の知識をQ&A形式で解説した資料を無料配布しています。
◆この資料でわかること
- 曖昧になりがちな「勤務時間」と「労働時間」の明確な違い
- 年間労働時間の算出など、給与計算にも関わる重要知識
- トラブルを未然に防ぐための休憩時間の付与ルール
- 罰則リスクを回避するための正しい勤怠管理のポイント
労務リスクへの備えは、企業の信頼を守る第一歩です。自社の勤怠管理体制の見直しに役立ちますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
-


人件費削減の方法とは?具体的な方法や失敗しないためのポイント
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
労働時間の関連記事
-


副業の労働時間通算ルールはいつから見直される?改正の最新動向
勤怠・給与計算公開日:2025.12.17更新日:2026.01.15
-


着替えは労働時間に含まれる?具体的なケースや判例を交えながら分かりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2025.04.16更新日:2025.10.06
-


過重労働に該当する基準は?長時間労働との違いや影響を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.02.16更新日:2025.08.19