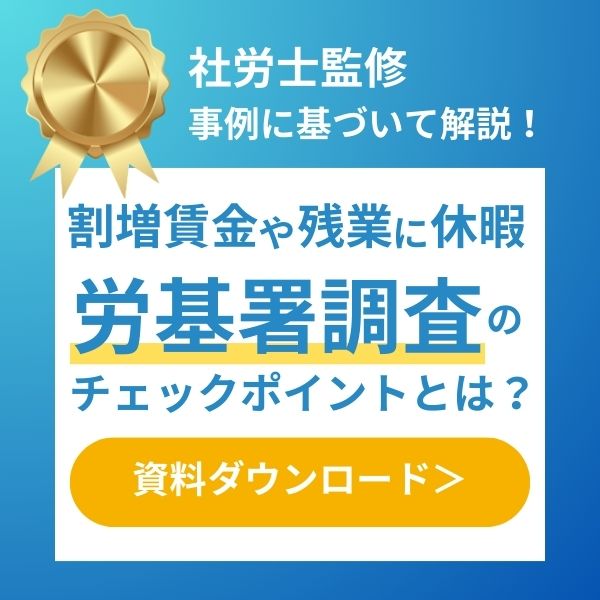中小企業向けの勤怠管理システムとは?選び方と業種別のポイントを解説
更新日: 2025.3.27 公開日: 2020.1.28 jinjer Blog 編集部

集計作業など何かと手間のかかる勤怠管理は、マンパワーが限られている中小企業にとっては負担の大きい業務の一つです。「従業員が増加して、タイムカードや出勤簿では勤怠管理をおこなえなくなった」「人事担当の業務が圧迫している」といった勤怠管理の悩みを抱える企業もあるでしょう。
今回は、中小企業のシステム導入前の課題、導入後の効果をご紹介し、導入すべき勤怠管理システムや選ぶ際のポイントを公開します。
関連記事:勤怠管理システムとは?はじめての導入にはクラウド型がおすすめ
目次

人事労務担当者の実務の中で、勤怠管理は残業や深夜労働・有休消化など給与計算に直結するため、正確な管理が求められる一方で、計算が複雑でミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、働き方が多様化したことで管理すべき情報も多く、管理方法と集計にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな担当者の方には、集計を自動化できる勤怠システムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 打刻漏れや勤務状況をリアルタイムで確認可能、複雑な労働時間の集計を自動化
- 有給休暇の残日数を従業員自身でいつでも確認可能、台帳の管理が不要に
- PCやスマホ・タブレットなど選べる打刻方法で、直行直帰やリモートワークにも対応
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
1. 中小企業向けの勤怠管理システムとは


まずは勤怠管理システムがどのようなものか解説していきます。導入前に知っておきたい中小企業に求められる勤怠管理システムの条件や導入率などと併せてみていきましょう。
1-1. そもそも勤怠管理システムとは
勤怠管理システムとは、従業員の出退勤時間の打刻、残業や有給取得の申請や管理、シフトの作成など勤怠に関わる業務を支援するシステムのことです。全従業員の勤怠をシステム上で一元管理できるため、残業時間の集計などさまざまな業務を大幅に省くことができます。
近年では、初期投資を抑えられる「クラウド型」が主流となりつつあることから、中小企業においても、クラウド型の勤怠管理システムを導入する企業が増えてきています。
関連記事:勤怠管理システムを導入する5つのメリットは?デメリットも解説!
1-2. 中堅・大企業向け勤怠管理システムとの違い
中堅・大企業向けの勤怠管理システムは、その規模に応じた複雑な機能が求められます。
例えば、複雑な就業規則や独自の人事制度への対応、細やかな権限設定、多拠点対応などが必要です。一方、中小企業向けのシステムは、よりシンプルで使いやすく、基本的な機能が充実しています。ただし、働き方改革による労務管理強化が求められているため、大企業向けに近い機能を提供する中小企業向けのシステムも増えています。従業員数が多い企業でも利用されることが増えているのが現状です。
1-3. 中小企業の勤怠システム導入率
勤怠システムの導入率は中小企業においても増加傾向にあります。2023年にjinjer株式会社が実施した調査によれば、物流・運送業界の企業の25.7%が勤怠管理システムへの移行を検討中、38.5%が取り組むかどうかを検討中と回答しています。
この結果からも分かるように、多くの中小企業が勤怠管理システムの導入に高い関心を持っています。今後も導入が進み、効果的な勤怠管理がおこなわれることが予想されます。
出典:jinjer株式会社「【2024年問題】物流・運送業界における勤怠管理の実態調査」
2. 中小企業によくある勤怠管理の課題

勤怠管理は業務の煩雑さから時間がかかりやすく、人手が足りない中小企業では悩みになっていることが多いです。どのような課題を抱えているのかみていきましょう。
2-1. 従業員増加・事業拡大の際に対応できない
中小企業では従業員の勤怠管理をタイムカードや出勤簿でおこなっていることが多いです。そのような場合、事業拡大やそれに伴う従業員の増員といった際に、規模によっては従業員の勤務状況を管理するのが困難になります。
また、人事担当者の負担軽減のために新たな人材を雇用するなど、人件費がかさんでしまうことにもなりかねません。これから事業の拡大や従業員の増員を考えている中小企業においては、勤怠管理システム導入にかかるコストと人件費を秤にかけてみることも必要でしょう。
2-2. 勤怠管理に割ける人材が足りない
手書きやタイムカードで勤怠管理をしている場合、集計や計算業務は複雑になりやすく、対応できる人材は限られます。大企業の場合には人事担当者もそれなりの数がいるでしょう。しかし、中小企業では担当者が1人しかいない、社長が対応しているという企業も多いのが現実です。
1人しかいない担当者が何らかの理由で会社を休んだり、急な病気にかかってしまったり、はたまた退職するといった場合には、人事業務が滞るといった不具合が生じることになります。
2-3. 法改正のたびに対応に追われてしまう
働き方改革をはじめとした労働環境や労働環境に関連する法律は改正がおこなわれやすいです。アナログな方法で管理をしている場合、法改正があるたびに対応に追われて現場が混乱するケースも多々あります。
また、気づかないうちに法律違反をしている恐れもあります。情報のアップデートが遅くなり、「去年まではこれで問題なかったのに」「以前はこのやり方で指摘されなかった」といった事態が起こりやすいのも中小企業の悩みになっています。
3. 勤怠管理システム導入で期待できる効果・メリット


前述したような中小企業ならではの課題を解決するには、勤怠管理システムの導入が効果的です。導入を検討する企業は増加傾向にありますが、どのような効果やメリットがあるのかまずは知っておきましょう。
3-1. 業務効率が向上する
勤怠システム導入により、目に見えて効果を実感できるのが業務の効率化でしょう。システム上で全従業員の勤怠情報が一元化されるため、毎月のタイムカードや出勤簿の回収作業が不要となります。労働時間の計算も自動でおこなえるため、集計作業も必要ありません。回収や集計など煩わしい作業がなくなることで、より重要な業務に時間を回すことができます。
さらに、導入することで従業員からの有給休暇や残業申請の管理も簡素化されるため、人事部門の負担が軽減されます。こうした変更によって、業務のスピードが向上するだけでなく、正確性も増し、全体の業務効率が大幅に改善されることが期待されます。その結果、企業全体の生産性向上にも寄与し、従業員の働く環境も整備されることで、モチベーションの向上にもつながるでしょう。
3-2. コストの削減につながる
タイムカードや出勤簿で勤怠管理をおこなう場合は、タイムカードや用紙などのコストに加えて、月末に本社へ送付するための郵送代も必要です。勤怠管理システムを導入すれば、システム上で一元管理できるため、これらの費用を削減することができます。給与明細の電子化までできれば、さらにコストは削減できるでしょう。
また、上述でも説明のとおり業務効率も上がるため、残業を伴って勤怠管理をおこなっていた場合は、人件費削減の効果も期待できるでしょう。
3-3. 法律を守った対応ができる
クラウド型の勤怠管理システムを活用することで、常に最新の法改正に自動で対応できるため、法的リスクも軽減します。法的なリスクがなくなることで、担当者はストレスや不安のない業務をしやすくなり、モチベーションの向上にもつながるはずです。割増率や税率の変更にも自動的に対応できるため、計算式の作り直しや計算ミスによる再チェックなどの時間を減らすことができるでしょう。
また、クラウド型の勤怠管理システムは、従業員がモバイルデバイスからもアクセスできるため、テレワークや外回りをしている社員も簡単に打刻や申請をおこなえる利便性があります。打刻忘れや申請漏れによるトラブルも防ぎやすくなります。
3-4. 人事戦略にも活用できる
勤怠管理システムの中には、従業員の勤怠状況をリアルタイムで把握し、数値化やグラフ化する分析機能を搭載しているものもあります。そういった機能を活用すれば、どの部署または時期に業務の逼迫がおきているかなど一目で把握できるようになるため、人材の適正配置など人事戦略に活かすことも可能です。
加えて、こうしたデータ分析機能は、従業員の労働時間の傾向や残業発生のパターンを明確に示します。これにより、企業は効率的な人員配置や、必要な自社内での研修計画を立てやすくなり、全体の生産性向上に繋がります。
また、適切な人事戦略を実行することで、従業員のモチベーション向上にも寄与し、多様な労働時間体系や勤務スタイルに柔軟に対応する企業としての印象を強化することもできます。
4. 中小企業へおすすめできる勤怠管理システムの選び方


中小企業が勤怠管理システムを導入し、大きな効果を得るにはシステム選びが非常に重要です。以下のポイントは特に意識して確認し、自社にとって本当に有用であるか時間をかけて精査しましょう。
4-1. 事業規模の拡大にも柔軟に対応できる
中小企業は伸びしろが多く、事業の方向性によっては大企業へと発展する可能性を大いに秘めています。事業規模の拡大やそれに伴う従業員の増員にも柔軟に対応可能な勤怠管理システムを選定しなければなりません。
これに加えて、導入する勤怠管理システムは、法改正への迅速な対応が可能であることも重要です。具体的には、自動アップデート機能があり、最新の労働基準法に基づく管理ができるシステムを選ぶことで、企業が法的リスクにさらされることが少なくなり、安心して業務を進めることができます。
また、クラウド型のシステムであれば、テレワークにも対応した柔軟な勤怠管理ができるため、従業員の満足度を向上させるだけでなく、企業全体の生産性を高めることにも寄与します。このように、中小企業が適切な勤怠管理システムを導入することは、事業成長のための重要なステップとなります。
4-2. 導入前にお試し期間の設定がある
中小企業が勤務管理システム導入で躊躇する点があるとすれば、それはコスト面でしょう。導入前にお試し期間設定があるシステムを選択すれば、事前のお試しで導入の価値があるか否かを判断することができます。また、自社の業務フローに合った機能を持つシステムを選択することは、長期的なコスト削減にもつながります。
また、システムのわかりやすさや使いやすさも重要です。実際に操作をしてみないと判断できない部分も多いため、お試し期間を使って操作感を確認できることは重要です。「機能はよいけど難しすぎて使いにくい」などといったケースを避けるために、できるだけお試し期間付きの製品を選びましょう。
4-3. 誰でも簡単に使用できる
正確な勤務実態の把握のためには、自社にあった打刻方法を選ぶことが重要です。導入したい打刻方法が定まっていない場合は、複数の選択肢があるものを選びましょう。例えばWeb打刻、ICカード、スマホアプリのほか、PCログオン・ログオフデータ収集ツールを使った打刻集計や、スマートロックの施錠・開錠情報と連動する打刻集計に対応しているものなどです。
また人事担当者の人材不足が懸念される中小企業では、その担当者が突然不在になったり欠員になったりした場合に、代行者を探すのは容易ではないでしょう。そのため、誰でも簡単に操作できる勤怠管理システムを導入すれば、そういった不測の事態においてもすぐに代行者を充てることができます。
4-4. 勤務形態・就業規則に合わせてカスタマイズできる
中小企業の中には、これから事業拡大や従業員の増加を考えているところもあるでしょう。そのため、正社員だけの雇用に留まらず、パートや派遣社員の雇用も視野に入れておかなくてはいけません。また、従業員が増えたことで社内の働き方を見直す機会がでてくることや、フレックスタイム制度など新たな制度が導入される可能性もあります。
これまでのタイムカードや出勤簿による勤怠管理であった場合、変化した勤務形態に合わせて、その都度人事が自ら勤怠管理の方法を修正しなくていけませんでした。しかし、勤務形態に合わせてカスタマイズできる勤怠管理システムを導入すれば、人事が自ら勤怠管理の方法を修正する必要がなくなります。多様な働き方が求められる現代で、今後どのように勤務形態が変わったとしても問題なく対応できるでしょう。
4-5. ワークフロー機能が搭載されている
承認ワークフローがあることで、プロセスの透明性が向上し、従業員が自らの勤務状況や休暇取得の状況を把握しやすくなるというメリットもあります。特に、忙しい職場環境においては、速やかな承認が求められます。システムによっては、承認者が不在の場合でも代理承認の機能があるため、業務が滞ることを防ぐことができます。
さらに、過去の申請履歴が確認できることで、給与計算や労働時間の集計にも役立ち、正確な勤怠管理が実現します。このように、ワークフロー機能が搭載されている勤怠管理システムは、企業の業務効率を高め、管理負担を軽減するための強力なツールとなります。
4-6. サポート体制が充実している
サポート体制に関しても、勤怠管理システム選びでは外せない要素の一つです。システムの使い方など不明点を尋ねたいときや、システムトラブルが発生した際など、どのように対応してもらえるのか、サポート内容についても導入前にしっかり確認しておきましょう。
システム会社によっては、サポート範囲が無料と有料で分かれているケースもあります。どの範囲まで無料でサポートしてもらえるのか、費用についても忘れずにチェックしましょう。
ここまで勤怠管理システムの選び方を紹介してきましたが、勤怠管理システムの導入を検討する際は、システムの比較検討~システム導入~運用開始までの流れを確認しておくことで、システム導入に必要な準備や運用開始までの期間を把握することが可能です。
当サイトでは、勤怠管理システムを導入して運用開始するまでにどのようなことが必要になるかをまとめた「勤怠管理システム導入完全ガイド」を無料で配布しているため、こちらより資料ダウンロードページをご覧ください。
関連記事:小規模企業や中小企業におすすめの勤怠管理システムとは?選び方を詳しく解説
5. 【特定の業界/業種向け】勤怠管理選びのポイント


中小企業の中でも特定の業界・業種によっては、特有の勤務形態や働き方に対応したシステムが必要になります。より効果的な導入ができるように、関連する業種の方はぜひ参考にしてください。
5-1. 病院・医療機関
病院・医療機関では、医師・看護師・技師・事務職員など複数の職種に加えて、様々な雇用形態や夜勤含めた勤務パターンがあり、勤怠管理も複雑になります。そのため、通常のオフィス向け勤怠管理システムよりも緻密なシフト作成機能が必要です。加えて、急な欠勤や残業に対する柔軟な対応が求められるため、リアルタイムでの勤怠状況の把握ができるシステムが望ましいです。
医療機関特有のニーズに応えるためには、各職種の勤務状況を一目で確認できるダッシュボードや、派遣スタッフの勤務管理機能を搭載した勤怠管理システムを選ぶことが重要です。これにより、医療行為に影響を及ぼすことなく、スムーズなシフト調整が実現できるでしょう。
5-2. 製造業
製造業では、人の入れ替わりが多いうえ、日本語や日本文化に不慣れな外国人労働者も増えているため、操作が複雑なシステムは向いていません。交通系ICカードの流用といった打刻方法や、熱・ホコリ・衝撃に強いタイムレコーダーなど、ソフト・ハードともに現場に即した勤怠管理システムがおすすめです。また、製造業においては、シフト制の勤務形態が一般的であるため、シフト管理機能が充実したシステムの導入が効果的です。
これにより、急な人員変更や欠勤に柔軟に対応でき、現場の生産性を維持しつつ、従業員の負担を軽減することが可能になります。さらに、テレワークの普及によって在宅勤務が増加している中で、移動中の打刻が可能なアプリケーションを搭載したシステムもその競争力を高めるポイントとなります。
5-3. 建設業
建設業では直行直帰が多く、社員の負担状況を正確に把握しにくいという課題があります。また、現場ごとに勤務場所が異なるため、移動や労働時間の管理が複雑になりがちです。これに対応するためには、GPS機能やモバイル端末での打刻が可能なシステムが有効です。さらに、建設業界に特化した勤怠管理システムでは、現場ごとの作業内容や勤務時間を詳細に記録できる機能が備わっています。
これにより、各現場の労働状況をリアルタイムで把握でき、必要な人員や労働時間の適正管理が可能になります。また、データが一元管理されることで、労働基準法への適合や安全衛生管理の面でも大きなメリットをもたらすでしょう。
5-4. 飲食業
飲食業では、店舗スタッフの正社員数が少ないことが多いです。正社員とアルバイトやパートの給与、アルバイトの中でも時給の違いなどもあるため、給与計算が複雑になります。また、忙しい時間帯と余裕のある時間帯や曜日の差が大きく、人員の配置を固定することが非常に困難です。タイムカードの打刻忘れを防ぐアラート機能も役立つでしょう。
そのため、シフト作成や給与計算業務の負担が大きく、それらをスムーズにこなせるシステムであることが重要です。飲食業は人材不足の現場が多いため、事務作業に割く時間を減らすことで店長やシフト管理者も接客に入りやすくなり、サービスの質を向上させることにもつながるでしょう。
5-5. 小売業
小売業も飲食業と同様に店舗に正社員が少なかったり、そもそも店舗にパソコンが置かれてなかったりするケースも存在します。その場合は、どのように打刻をするのか、管理に使う端末はどのようにするのかなどを考え、各店舗に適したシステムを取り入れることが重要です。
さらに、小売業はスタッフの入れ替わりが激しいこともあります。そのような場合は新しいスタッフが入るたびに打刻方法やルールを説明する必要があるため、シンプルかつなじみやすいシステムにするとよいでしょう。
5-6. IT関連業
IT業界は裁量労働制やフレックスタイム制、テレワークなど多様な働き方を導入している企業が目立ちます。そうした働き方にも対応できるようシステムであることに加え、従業員側も労働時間の自己管理がしやすいシステムが求められます。特に裁量労働制の場合は運用が正しくされていることを把握できるようなシステムであることを重視しましょう。
また、IT関連業では会社独自のルールが採用されているケースもあります。そのような場合はシステムがカスタマイズできるか、対応しきれるかなど、自社との相性も十分に確認しましょう。
6. 中小企業の勤怠管理システム導入事例


最後に、勤怠管理システムの導入によって企業の課題を解決した事例を2つご紹介します。
6-1. 正確な勤怠管理にくわえ不要な残業も減少
勤務形態が不規則であることから、労働時間の集計ミスの多さが課題となっていた企業の事例です。このような悩みは、テレワークやフレックスタイム制が一般的になったころから急激に増えてきました。
この企業の事例では、自社の勤務形態に合わせて柔軟にカスタマイズできる勤怠管理システムを導入したことにより、労働時間を正確に把握できるようになりました。また、システム上でまとめて管理できるようになったことで、3~4日かかっていた締め作業が2日に短縮されました。
さらに、残業についても、システムで申請してから上長が承認をおこなうフローに変化させています。これによって必要のない残業が減り、残業時間の削減にもつながったそうです。
6-2. 勤怠管理にかかる作業工数の大幅な削減に成功
従業員の増員にともない、タイムカードでの勤怠管理に限界を感じていた企業の事例です。タイムカードの集計だけでも大きな負担でしたが、加えて押し忘れや打刻ミスの確認作業も多かったため、担当者は月末になると業務に追われる状態になっていました。
勤怠管理システム導入によってペーパーレス化を実現できただけでなく、タイムカードの回収や集計にかかる工数も大幅に削減できました。打刻アラート機能によって、打刻忘れも減らせるようになり、確認にとられる時間の削減にも成功しています。
くわえて、残業や有給の申請も、従来の紙からシステムに変ったことで、従業員側でリアルタイムに確認できるようになり、残業や有給に関する問い合わせを減らすことができました。
7. 中小企業の勤怠管理の課題は勤怠管理システムの導入で解決しやすくなる


中小企業では勤怠管理に課題を抱えているケースが多く、業務負担が偏っているケースが多々見られます。
特にこれから事業拡大を狙おうとする中小企業の中には、これまでのタイムカードや出勤簿による勤怠管理に限界を感じている企業も多いことでしょう。
しかし勤怠管理システムなら、そんな悩みを一気に解決してくれます。勤怠管理システムを使用し、効率的な勤怠管理をおこないましょう。



人事労務担当者の実務の中で、勤怠管理は残業や深夜労働・有休消化など給与計算に直結するため、正確な管理が求められる一方で、計算が複雑でミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、働き方が多様化したことで管理すべき情報も多く、管理方法と集計にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな担当者の方には、集計を自動化できる勤怠システムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 打刻漏れや勤務状況をリアルタイムで確認可能、複雑な労働時間の集計を自動化
- 有給休暇の残日数を従業員自身でいつでも確認可能、台帳の管理が不要に
- PCやスマホ・タブレットなど選べる打刻方法で、直行直帰やリモートワークにも対応
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
中小企業の関連記事
-


小規模企業や中小企業におすすめの勤怠管理システムとは?選び方を詳しく解説
勤怠・給与計算公開日:2023.11.30更新日:2025.07.18
-


中小企業にも人事評価制度は必要?導入率や導入方法を解説
人事・労務管理公開日:2023.06.19更新日:2025.04.17
-


人事評価システムは必要?比較する際におすすめの選び方やメリットを解説
人事・労務管理公開日:2023.06.02更新日:2025.04.17
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
-


人件費削減の方法とは?具体的な方法や失敗しないためのポイント
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
勤怠管理の関連記事
-

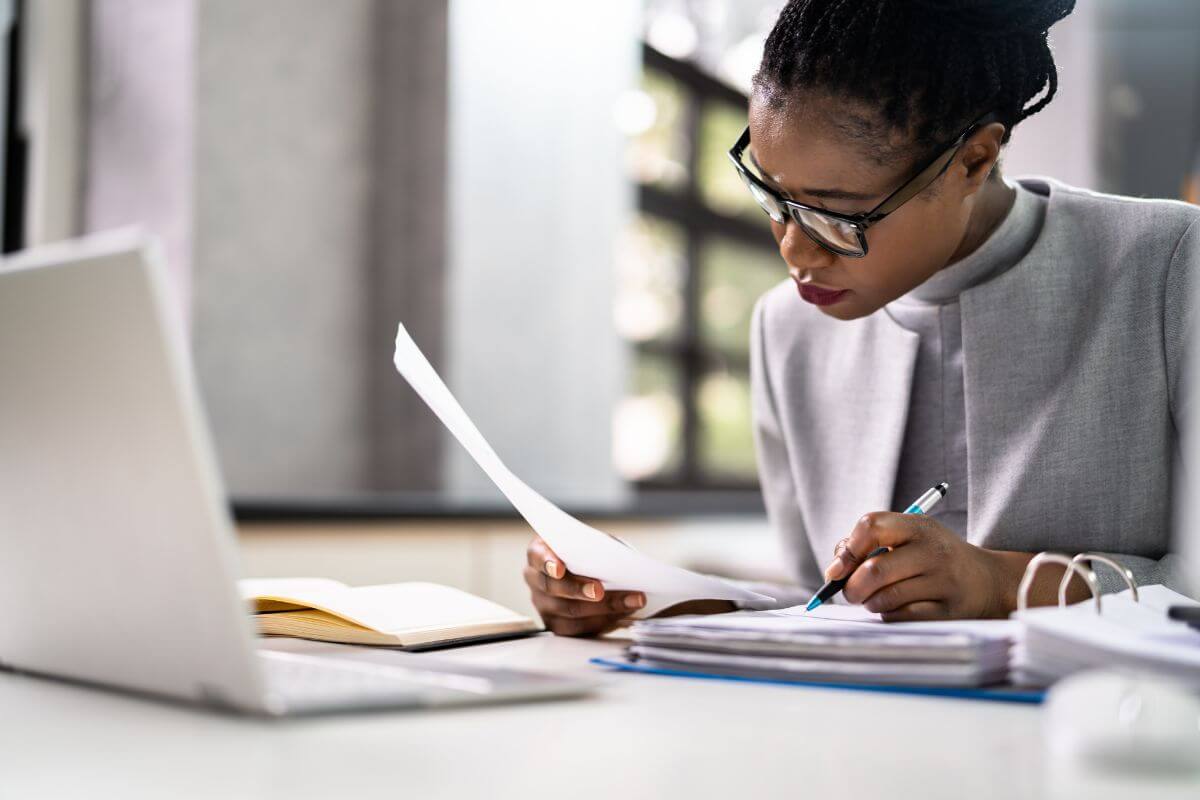
法定四帳簿とは?電子化の可否・保存期間・規則を破った場合の罰則を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.03.09更新日:2025.02.21
-


残業の過労死ラインとは?時間・管理職の場合・企業の対策を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.01.31更新日:2025.01.31
-

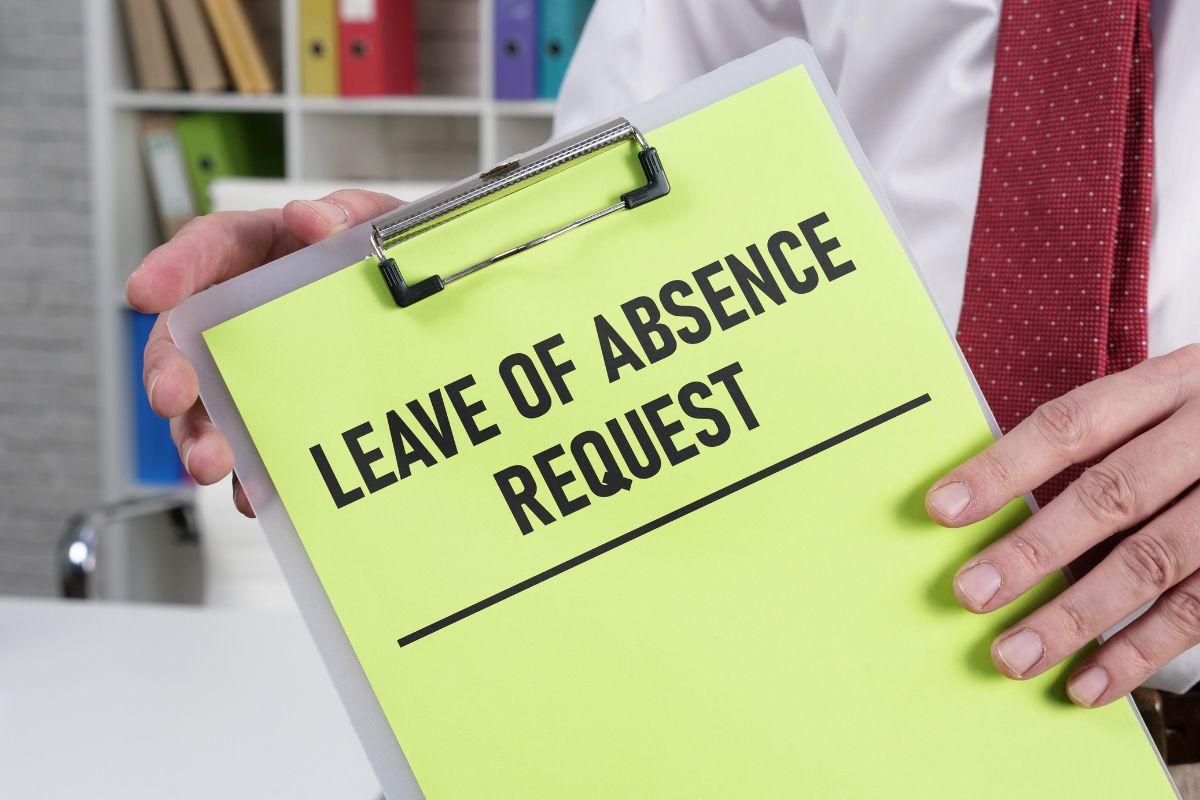
欠勤とは?休職との違いや欠勤控除の方法を解説
勤怠・給与計算公開日:2024.12.21更新日:2025.05.02