正社員でも雇用契約書は毎年の更新が必要?理由や注意点を解説
更新日: 2025.8.4 公開日: 2020.12.7 jinjer Blog 編集部

正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、働き始めるときには全ての労働者と雇用契約書を交わすのが一般的です。
しかし、更新に関しては、正社員は契約期間が決められているわけではないため、「一度雇用契約書を交わしてしまえば更新の必要はない」と思っている担当者の方もいるかもしれません。
ただ、勘違いや見落としなどが原因で発生する社員と企業の間のトラブルを避けるには、定期的に契約書の更新をおこなうのが望ましいといえます。
本記事では、正社員でも毎年雇用契約書を更新した方が良い理由や、雇用契約書を更新する際の注意点などについて解説します。
関連記事:雇用契約の定義や労働契約との違いなど基礎知識を解説
関連記事:正社員の雇用で必須の雇用契約書の作成方法を分かりやすく解説
目次

雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。
法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。
◆押さえておくべきポイント
- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)
- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)
- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成
- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策
いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 雇用契約書とは


雇用契約書とは、雇用主(会社側)と労働者(従業員)の間でどのような労働契約が結ばれるのかが記載されている契約書です。
労働契約の主な内容は、以下のような項目があります。
- 給与
- 就業時間
- 労働契約期間
- 業務内容
- 就業場所
- 昇給や退職
これらの労働条件に関連する重要事項を定め、書面化したものが雇用契約書です。この契約書に、会社側と従業員が署名捺印することで、労働契約が締結されます。契約書であるため、雇用契約書には法的な効力があります。
雇用契約書と似た内容を記載する書類に「労働条件通知書」があります。こちらは作成の義務が企業にあり、この義務を怠ると労働基準法に違反したとみなされてしまいます。
そのため、雇用契約書と労働条件通知書をそれぞれ作成して交付する必要があります。条件を満たせば両書類の役割を担った「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成することも可能です。
2. 正社員の雇用契約書は毎年作成しなくてもよい


雇用契約の内容は「使用者が労働者を雇用するときに明示しなければならない」と定められています。
正社員は一般的には契約期間の定めがない無期雇用契約です。この原則に従うと、入社時に雇用契約書を取り交わせば、契約内容に変更がない限り毎年作成する必要はありません。
しかし、雇用契約書の見直しを自主的におこなう従業員は非常に少なく、契約内容を意識して働いている人も少数です。そのため、時間の経過とともに雇用契約の内容を忘れたり、無意識に誤った認識になっていたりすることがあります。
それが原因でトラブルになる可能性もあるため、可能であれば正社員でも毎年雇用契約書を作成し、見直す機会を作りましょう。
雇用契約書の作成と見直しをおこなうことで従業員とのコミュニケーションも取りやすくなり、現場が抱えている問題や不満の早期発見につながる可能性もあります。
3. 有期契約の場合は雇用契約書の更新が必要

雇用契約書は雇用契約を交わすときに作成される書類であり、勤務地や業務内容・休日・給与などといった労働条件に関する内容が書面としてまとめられています。
労働条件として記載されている内容のひとつに「労働契約の期間」がありますが、契約社員や派遣社員の場合は、契約期間があらかじめ決められた「有期契約」という形で働くことになります。
有期契約での契約となる場合、例えば契約期間が3年間だったとすると、働き始めて3年が経過したあとの契約がどうなるかは、契約満了の時期を迎えるまでわかりません。
あらかじめ決められた契約期間が終わったときに、企業が社員にそのまま引き続き働き続けてほしい場合は雇用契約書を更新することになり、契約を更新するつもりがない場合はそのまま契約終了となります。
そのため、社員と有期契約を交わしている場合、雇用契約書の更新が必要になります。
令和6年4月から労働条件明示のルールが変更され、有期労働契約の更新時に雇い入れ直後の就業場所・業務の内容とこれらの変更の範囲の明示が必要になりました。最新の情報を確認し、漏れがないようにしましょう。
関連記事:雇用契約書が正社員でも必要な場合と不要な場合の違いとは?
関連記事:有期雇用契約書に正社員登用についての条件記載は必須?作成ポイントも解説!
参考:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます|厚生労働省
4. 正社員でも雇用契約書の更新が必要なケース


無期雇用である正社員は雇用契約書の更新が必須ではありませんでした。しかし、労働条件に変更があった場合は、契約書の内容を見直す必要があります。
4-1. 労働条件に変更があった場合
正社員は無期雇用であるため、雇用契約書の更新はしなくてもよいとお話をしました。
しかし、労働条件に変更があり、雇用契約の内容が変化した場合は最新のものに更新した上で作成・交付しなおさなければなりません。古い雇用契約の内容のまま放置してしまうと、実際の労働と雇用契約書の内容にずれが生じてしまい、トラブルに発展する恐れがあるからです。
労働条件がどのように変化し、雇用契約の内容がその内容に沿っていることを従業員にも確認してもらう意味も込めて、些細な労働条件の変化でも必ず更新するようにしましょう。
4-2. 可能であれば毎年更新することが望ましい
「2. 正社員の雇用契約書は毎年作成しなくてもよい」でも触れた内容ですが、労働条件に変更がない場合でも雇用契約書は毎年の更新が望ましいです。
とはいえ、社員数の多い大企業ともなると、すべての正社員に対して毎年契約書の更新をおこなうのは、手間やコストのことを考えるとなかなか難しいかもしれません。
そのため、すべての社員に対して毎年雇用契約書の更新をするのではなく、一定の社員にのみ雇用契約書の更新をするという選択肢も考えられます。例えば、昇進や昇給などで毎月の給料に変化があった場合、本来であれば給与辞令を交付するだけでOKですが、その際に契約書の更新もする形にするのです。
こうすることで、毎年すべての社員に対して契約書の更新をする手間を避けながら、定期的に労働条件の再確認や突き合わせをすることが可能になります。労働条件に特段の変化がない社員に対しては、その年は雇用契約書の更新手続きを取らなくてもよいでしょう。
関連記事:雇用契約を更新する手順|従業員に対して実施すべき具体的対応を解説
5. 正社員の雇用契約書を更新する場合の注意点

正社員の雇用契約書を更新する場合は、労働条件の記載内容に漏れがないかを確認し、従業員にもその内容を確認してもらうことが大切です。
5-1. 労働条件が網羅されているかを確認する
近年、働き方改革などの影響により多様な働き方が推進されるようになり、従来の働き方以外にフレックス制や裁量労働制のような働き方を採用している企業も増えてきました。
また、新型コロナウイルスの感染拡大も働き方に大きな影響を与えており、会社に出社せずに在宅やリモートで仕事をしている社員も増えてきています。
「雇用契約書を作成した時点ではそういった働き方は想定していなかった」という可能性も高いため、以前雇用契約書を更新したときから働き方が大きく変わっている場合は、雇用契約書の内容を新しい働き方に対応させなければなりません。
雇用契約書を初めて取り交わしたときから労働条件に関する何らかの変化が起きる可能性は、今後ますます高くなっていくと考えられるため、雇用契約書を更新する際は労働条件がきちんと網羅されていることを、しっかり確認する必要があります。また、雇用契約の見直し・修正をする際には、就業規則と労働条件通知書、法律の優先順位には気を付けながら実施し、雇用契約にも反映させるようにしましょう。
当サイトでは、上述したような雇用契約を考える上での優先順位のことや禁止事項などを解説した資料を無料で配布しております。見直しをしていく中で、雇用契約に関して不安な点を見つけた方は、こちらから資料をダウンロードして、問題ないかご確認ください。
関連記事:労働条件通知書と雇用契約書の違い|それぞれの役割と発行方法を解説
有期雇用の場合は労働条件明示のルール変更に注意しよう
有期雇用の場合は、労働条件明示のルール変更に注意しましょう。ルール改正は令和6年4月に施行されていますが、有期雇用に関する変更事項は今一度確認しておくことが重要です。
有期雇用へのルール変更は下記の2点です。
- 更新上限の有無と内容
- 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件
更新上限は単に有無を記載するだけでなく、新設したり短縮したりする場合は、その理由を必ず明示する必要があります。また、「無期転換申込機会と無期転換後の労働条件」では、正社員の労働条件とのバランスをしっかり考慮しなければなりません。
明確な理由がなかったり、有期雇用が不当な労働条件だったりすると労働基準法違反になってしまうこともあるため注意してください。
参考:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます|厚生労働省
5-2. 提出期限を設けて雇用契約書の内容を確認してもらう
従業員に雇用契約書の内容について説明をおこなった後は、一旦持ち帰ってもらい、内容をじっくり確認してもらうようにしましょう。
その場でサインや捺印を求めてしまうと、従業員から「内容を確認する時間を与えられなかった」と主張され、後々トラブルになる可能性があります。
そもそも雇用契約の更新は、労働条件の認識のずれを埋める目的もあるため、労働者に雇用契約の内容をしっかり理解してもらわなくてはいけません。
そのためには、翌日や2日後など提出期限を設けて、雇用契約書の内容を確認する時間を与えることが大切です。
6. 雇用契約書を毎年更新して認識のずれを防ぐことを心がけよう
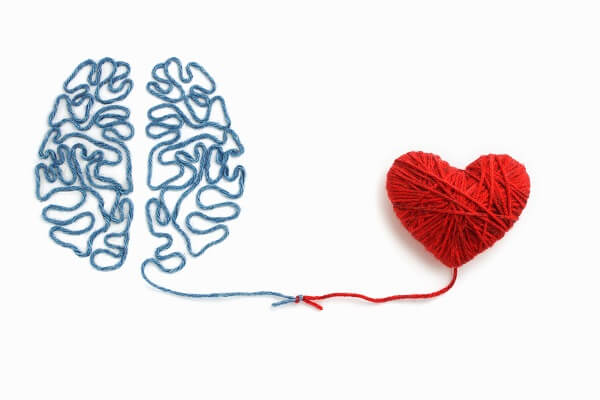
正社員は基本的に有期契約ではないため、毎年雇用契約書を更新する必要はありません。しかし、労働条件を再確認して認識のずれや勘違いなどを防ぐという観点からすれば、雇用契約書を毎年更新することには意味があります。
もしも、毎年の更新がコストや手間がかかるなどの問題で難しいという場合は、昇給したタイミングに限定するなどでもよいため、定期的に雇用契約書の更新をおこなうことを心がけましょう。
ただし、業務負担が増えるというだけが理由であれば、システムの導入を検討するのもおすすめです。システムを導入して電子化すれば、メールで送るだけになるため、面倒な更新業務の効率化が期待できます。電子化について気になる方は以下の関連記事をご覧ください。
関連記事:雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?
関連記事:飲食店で正社員を採用する際の雇用契約書の作成方法・必要な手続き



雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。
法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。
◆押さえておくべきポイント
- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)
- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)
- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成
- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策
いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
雇用契約書の関連記事
-


雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや作成時の注意点を解説!
人事・労務管理公開日:2023.06.01更新日:2025.06.09
-


雇用契約書と労働条件通知書は兼用できる?兼用のメリットや作成方法、注意点をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2020.12.07更新日:2026.02.02
-

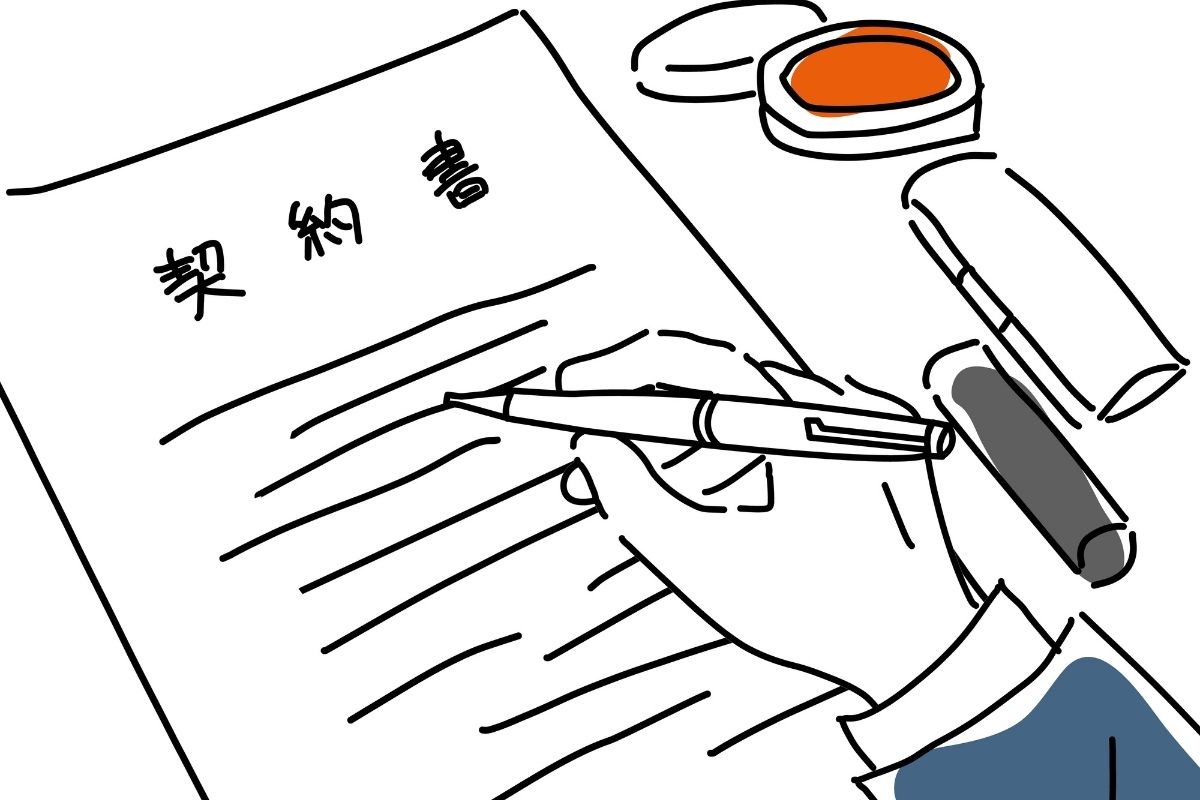
有期雇用契約書に正社員登用についての条件記載は必須?作成ポイントも解説!
人事・労務管理公開日:2020.12.07更新日:2025.12.24





















