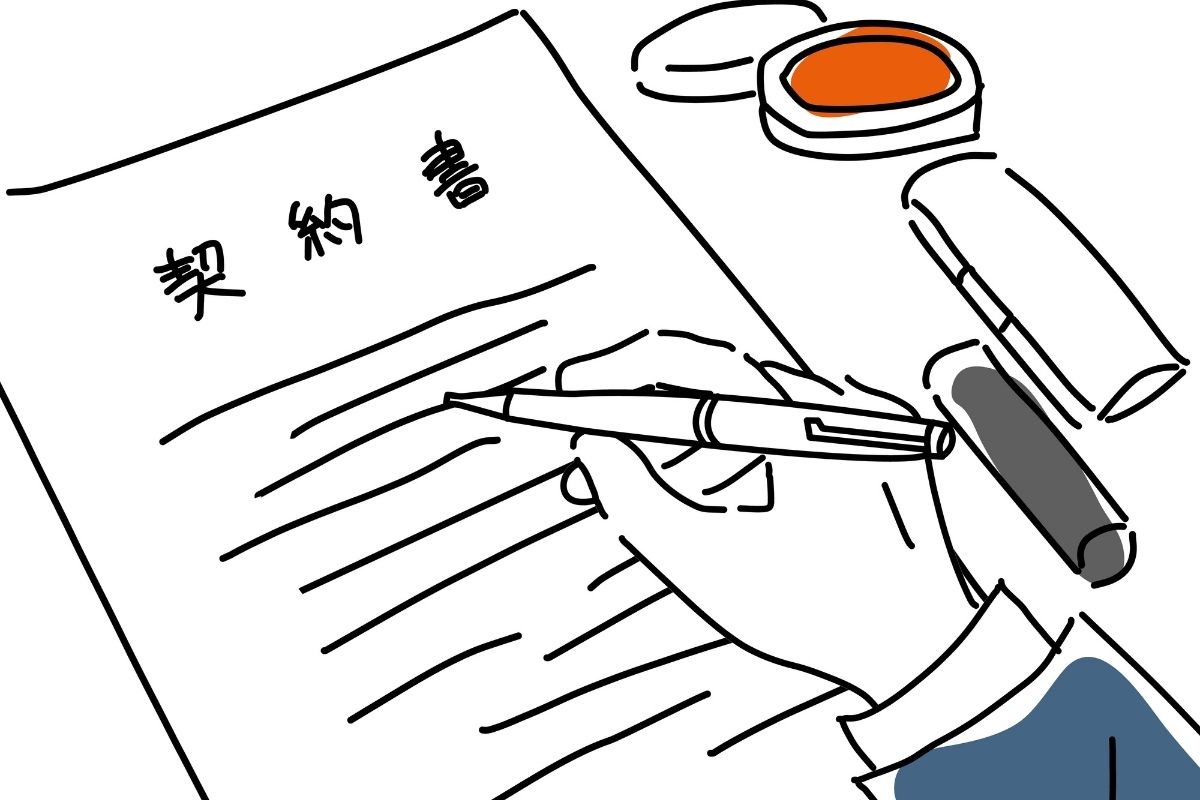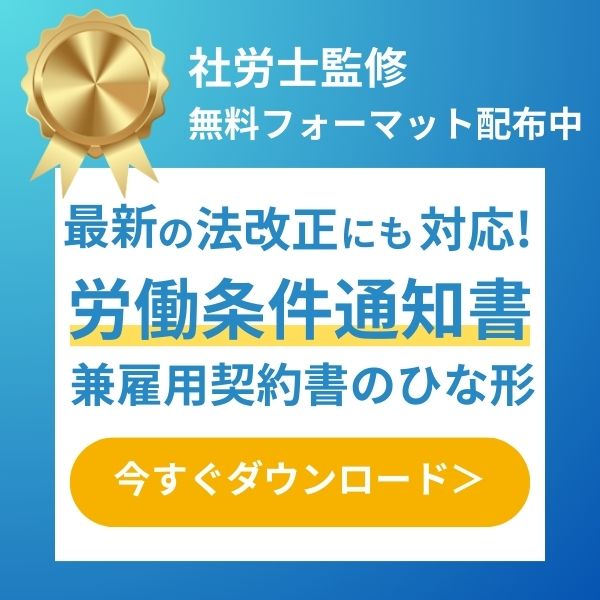パートタイマーの雇用契約書は必要?書き方のポイントを解説
更新日: 2025.12.24 公開日: 2020.11.16 jinjer Blog 編集部

パートタイマーに限らず、雇用契約書には法的な発行義務はありません。また、作成する場合の記載項目・記載内容も企業が決めてよいものです。
しかし、人手不足が進む中、パートタイム労働者(パートタイマー)を雇用する企業が増加しており、それに伴って雇用トラブルも増加傾向にあります。そのため、企業としては採用時に適切な雇用契約を結ぶ必要があります。
本記事ではパートタイマーの雇用契約書を作成・発行する際に確認すべきポイントを紹介します。
関連記事:雇用契約の定義や労働契約との違いなど基礎知識を解説
目次
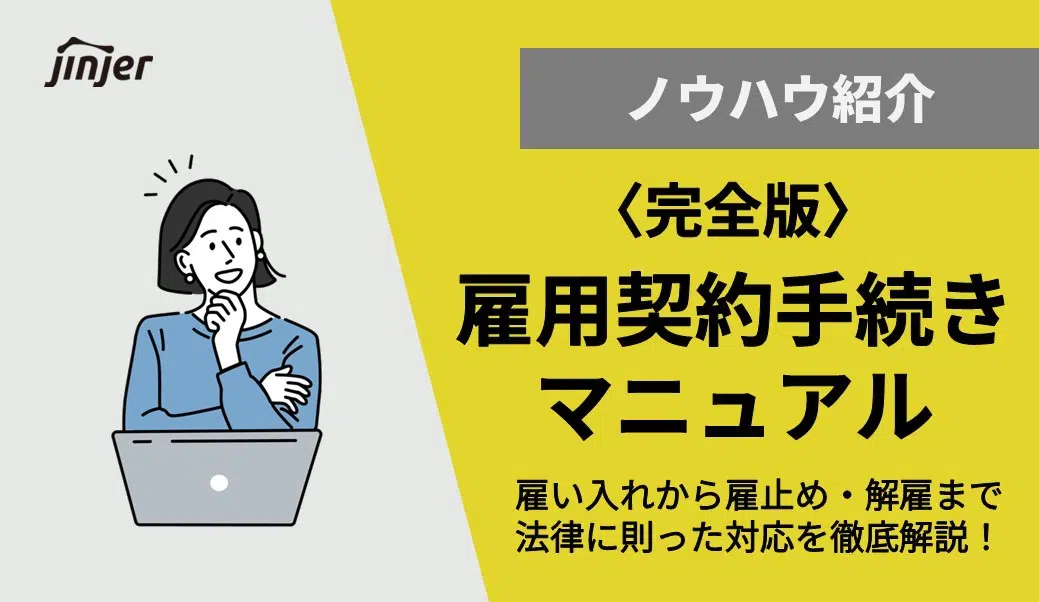
「長年この方法でやってきたから大丈夫」と思っていても、気づかぬうちに法改正や判例の変更により、自社の雇用契約がリスクを抱えているケースがあります。
従業員との無用なトラブルを避けるためにも、一度立ち止まって自社の対応を見直しませんか?
◆貴社の対応は万全ですか?セルフチェックリスト
- □ 労働条件通知書の「絶対的明示事項」を全て記載できているか
- □ 有期契約社員への「無期転換申込機会」の明示を忘れていないか
- □ 解雇予告のルールや、解雇が制限されるケースを正しく理解しているか
- □ 口頭での約束など、後にトラブルの火種となりうる慣行はないか
一つでも不安な項目があれば、正しい手続きの参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 雇用契約書とは
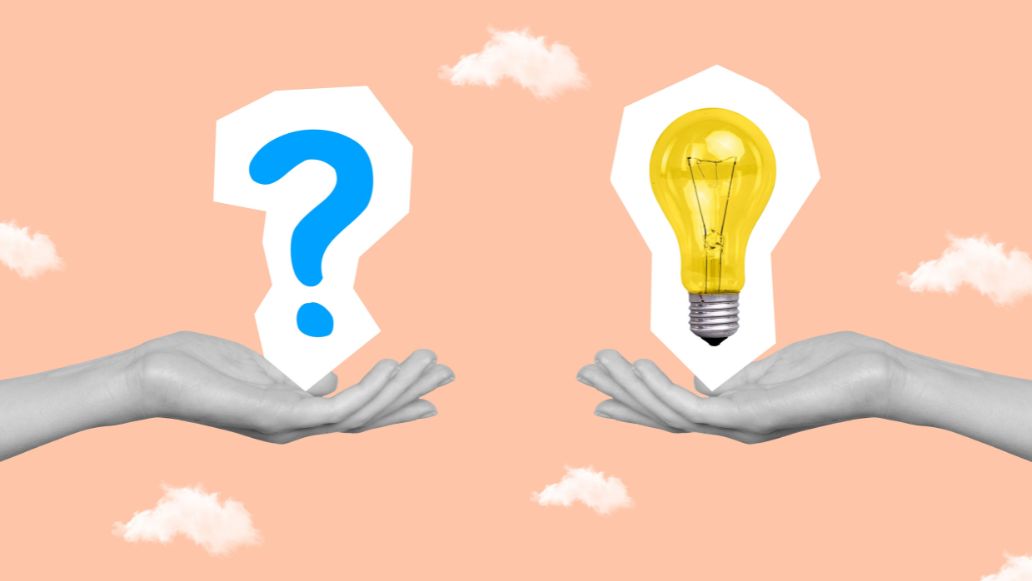
まずは雇用契約書とはどのような書類なのか、作成する意味や労働条件通知書との違いなど、基本的な部分を確認しておきましょう。
1-1. 労働契約の内容に合意したことを示す書類
雇用契約書は、企業や経営者と労働者の間で交わされる重要な文書です。この契約書により、雇用に関する条件や約束事に双方が同意したとみなされます。
雇用契約書に給与や労働時間、福利厚生などの項目を記載することで、労働者の権利を保護すると同時に、雇用主の法的拘束力も確保できます。
雇用契約書の作成は法的に義務付けられているわけではありません。しかし、契約の内容を書面として形に残さないまま雇用すると、後々トラブルの原因になることもあるため注意が必要です。
従業員を安心して雇用するためにも、取り交わした契約内容を形に残せる雇用契約書を作成することを推奨します。
円滑な雇用関係を築き、将来的なトラブルを回避するためにも、雇用契約書の作成は欠かせません。
関連記事:雇用契約書とは?記載すべき事項や作成方法をわかりやすく解説
1-2. 雇用契約書と労働条件通知書の違い
労働条件通知書は、労働基準法第15条で作成・交付が義務付けられている書類で、使用者が労働者を雇用する際、労働者に対して労働条件を明示するものです。
労働条件通知書には、必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」と制度を設ける場合に明示しなければならない「相対的明示事項」の2つの項目があります。
また、パートやアルバイトの場合はパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の定めにより、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の4つの項目を書面で明示することが義務付けられています。
雇用契約書には法的に記載が義務付けられている項目はありませんが、労働条件通知書には記載しなければならない項目があるという点が大きな違いです。
また、雇用契約書は使用者と労働者の双方の意思を確認し合意するものに対して、労働条件通知書は使用者が労働者に向けて労働条件を提示しているものであるため、雇用契約書と比較すると一方向のやり取りというニュアンスが強くなります。
関連記事:労働条件通知書と雇用契約書の違い|それぞれの役割と発行方法を解説
1-3. 労働条件通知書の発行のみでも問題ない
雇用契約は口頭でも成立するため、雇用契約書を書面として作成しなくても問題ありません。その代わり、労働条件通知書は作成・交付が法的に義務付けられているため、必ず作成する必要があります。
すなわち、新たな従業員を雇用する際は、労働条件通知書のみ書面で発行し雇用契約は口頭で実施する、としても成立するのです。
ただし、書面に残さずに雇用契約書を取り交わすのはリスクがあります。後になって従業員から「契約はしていない」「契約内容に合意をしていない」と言われてしまったとき、反論することが難しくなってしまいます。
こうした問題を解消し、2種類の書類を作成する手間を省きたい場合は、雇用契約書と労働条件通知書が一体化した「労働条件通知書兼雇用契約書」の作成をおすすめします。
当サイトでは、実際に、サンプルとして労働条件通知書と雇用契約書を兼用できるフォーマットを無料配布しています。
社労士の監修付きで、令和6年に労働条件の明示ルールが変更された点も反映した最新のフォーマットです。労働条件通知書と雇用契約書を兼用することができる雛形になっているため、「これから作る雇用契約書の土台にしたい」「労働条件通知書を更新する際の参考にしたい」という方は、ぜひこちらからダウンロードの上、お役立てください。
関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の兼用が可能?メリットや作成方法を解説
2. パートタイム労働者にも雇用契約書は必要?
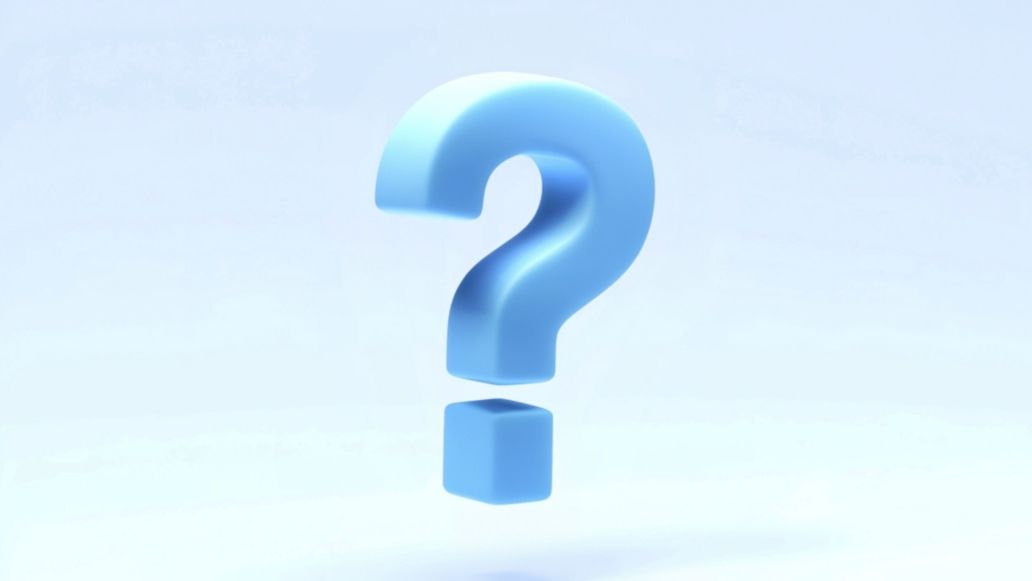
前項でも述べたように、雇用契約書は必ずしも必要なものではありません。パートタイム労働者に対しても同様で、書面にしなくてもよいものです。
しかし、パートタイム労働者は労働時間の変動や雇用期間の定めがあるケースも多いため、いわゆる「言った言わない」のトラブルが起きることがあります。
その際に雇用契約書がないと「合意していない」「聞いていない」と押し通されてしまうリスクがあるため、雇用契約の内容とそれに合意がされていることの証拠として、雇用契約書は作成したほうがよいでしょう。
また、雇用契約書を作成することでパートタイム労働者側も「この内容に合意している」という認識ができるため、トラブル防止にもつながります。
3. パートタイム労働者(パートタイマー)と雇用契約する時のポイント
 パートタイム労働者(パートタイマー)と雇用契約する場合は、まずはパートタイマーが法律上どのような位置づけにあるのか確認する必要があります。
パートタイム労働者(パートタイマー)と雇用契約する場合は、まずはパートタイマーが法律上どのような位置づけにあるのか確認する必要があります。
「パートタイム労働者」
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
ここでいう、「通常の労働者」とは、事業所において社会通念にしたがい「通常」と判断される労働者をいいます。この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。例えば、労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である、など雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。
事業所に同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパートタイム労働者となります。
ここでいう「通常の労働者」とは、労働契約の期間の定めがない無期雇用契約者や、長期雇用を前提とした待遇を受けている者のことで、基本的に「正社員」や「正職員」を指します。
また、「主婦がパート」「学生はアルバイト」というイメージがあるかもしれませんが、法律上ではアルバイトとパートに明確な違いはありません。
これらの定義を踏まえたうえで、ここではパートタイマーと雇用契約する時のポイントを紹介します。
3-1. パートタイマーとの雇用契約時に必要なこと
前述のように、パートタイマーは所定労働時間が短く、正社員とは異なる雇用形態となります。
しかし、正社員と同様に企業が雇用する労働者であることに変わりはないため「労働条件通知書」を作成し、書面で労働条件を通知することが法律で義務付けられています。
参考:労働基準法|e-Gov
また、短時間・有期雇用の場合は労働条件通知書で明示すべき項目が追加されます。パートタイム労働者は該当することが多いため、注意しましょう。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
この4項目が追加で必要になるため、正社員とは別の労働条件通知書が必要です。
当サイトでは、雇用契約の基礎知識や結び方のルール、禁止事項などを解説した資料を無料で配布しております。雇用契約に関して不安な点がある方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:労働条件通知書と雇用契約書の違い|それぞれの役割と発行方法を解説
参考:パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために|厚生労働省
3-2. パートタイマー雇用に関する法律を守る
長らく正社員とパートタイマーの間にある不当な格差は大きな社会問題として取り上げられており、国は法制度の整備を進めている状況です。これまでも関連する法案が成立し、企業は対応を求められてきました。
パートタイマーと正社員の違いを明確に区別できていなかった企業や、労働条件の提示が十分でなかった企業は、パートタイマーに作成していた雇用契約書や労働条件通知書を再度見直す必要があるかもしれません。また、パートタイマーの待遇そのものを見直す必要もあります。
最近の法改正の内容を確認し、自社の規則や対応に問題がないか十分に確認しましょう。
①同一労働同一賃金の施行
これまでは、正社員と同等の労働に従事しているにも関わらず、それでいて賃金や待遇は改善されないパートタイマーが多く存在していました。
このような状況に対して、国は同一企業内における正社員とパートタイマーとの間の不合理な待遇の差をなくすため、2020年4月1日より「パートタイム・有期雇用労働法」の施行を開始しました。
同法では、能力や経験、業績や成果、勤続年数等が正社員と同一であると判断された場合、パートタイマーと正社員の間に待遇差をつけることを禁止しています。
つまり、正社員と同等の責務を負い、同一の業務をこなしている場合、パートタイマーは正社員とほぼ同じ待遇を受けることが可能となっています。
パートタイマーにどのような業務・責務を与えるかは企業によって異なりますが、正社員と同等の仕事を任せる場合、待遇も正社員と均等にしなければならないことを念頭に置いておきましょう。
②パートタイマーの社会保険加入義務に関する法改正
パートタイマーと正社員の待遇差は、雇用期間や賃金だけでなく、社会保険など福利厚生の適応範囲にも及んでいます。
かつて、パートタイマーが厚生年金保険や健康保険に加入するには、週30時間以上の労働が条件となっており、条件に満たないパートタイマーは社会保険への加入が認められていませんでした。
しかし、平成28年10月からは従業員501人以上の会社で週20時間以上働く従業員などにも加入対象が拡大されました。
この条件は段階的に引き下げられており、2024年10月からは従業員数が51人以上の企業(特定適用事業所)も義務的適用の範囲に入っています。これによって多くの企業で働くパートタイム労働者が社会保険に加入できるようになりました。
社会保険に加入すれば、より手厚い保障を受けられるようになり、パートタイマーの待遇改善につながります。
関連記事:アルバイト採用でも雇用契約書は必要?作成するための4つのポイント
4. パートタイマーの雇用契約書の書き方

パートタイマーを採用する際に必要な雇用契約書には、下記の2点を押さえておくことが求められます。
- 法律で定められた労働条件を明示する
- 「有期雇用契約」「無期雇用契約」のいずれかを選択する
ここでは、この2つのポイントについて詳しく解説します。
4-1. 法律で定められた労働条件を明示する
労働基準法第15条では、使用者(雇用主)は労働契約(雇用契約)を締結するにあたり、労働者に対して賃金や労働時間などの労働条件を明示することが義務づけられています。
これは、「労働条件通知書」として通知するだけでなく、双方の署名・捺印を取り交わす雇用契約書の中にも必ず記載するようにしましょう。
「労働基準法施行規則」と、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(パートタイム労働法施行規則)」では、労働者に対して明示しなければならない労働条件として、以下の項目を掲げています。
①労働契約の期間
②労働契約を更新する場合の基準(労働契約を更新する場合があるものの締結に限る)
③就業場所
④従事すべき業務の内容
⑤始業及び終業の時刻
⑥所定労働時間を超える労働の有無
⑦休憩時間
⑧休日・休暇
⑨労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑩賃金の決定、計算方法、締め切り、支払い時期
⑪退職に関する事項(解雇の事由含む)
⑫昇給の有無
⑬賞与の有無
⑭退職手当の有無
⑮短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
このうち、⑫~⑭はパートタイム労働法施行規則により記載が義務付けられているものとなり、雇用するパートタイマーが希望した場合はFAX送信や電子メールなどで伝えても良いとされています。
しかし、中にはきちんとした書面で契約を締結することを希望する従業員もいるため、今後も継続的にパートタイマーを採用する予定がある場合は、パートタイマー専用の雇用契約書を作成しておいた方がよいでしょう。
なお、上記15の項目以外にも、企業が独自に規定を設けている場合は、必要に応じて以下の項目も追記します。
⑯退職金が支払われる労働者の範囲
⑰退職金の決定、計算および支払いの方法、時期
⑱臨時に支払われる賃金や賞与、最低賃金に関する事項
⑲労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
⑳安全および衛生に関する事項
㉑職業訓練に関する事項
㉒災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
㉓表彰および制裁に関する事項
㉔休職に関する事項
これらは、必ずしも書面にする必要はなく、口頭で伝えても可とされています。しかし、口頭のみの説明では後日内容を再確認したくなった際に、労働者から再度雇用主に労働契約について問い合わせなければなりません。
労働者がいつでも好きな時に雇用契約を確認できるよう、⑯以降の項目についてもなるべく書面にして提示した方がよいでしょう。
2024年の法改正による変更点
これらの内容を義務づけている労働基準法は、2024年4月に下記の点が改正されています。
- 就業場所や業務内容の変更範囲
- 更新上限の有無とその理由
- 無期転換権の申込機会
- 無期転換後の労働条件
これらの改正点は明示する必要があるため、雇用契約書の項目に齟齬がないよう、担当者は必ず確認しておきましょう。
参考:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(リーフレット)|厚生労働省
4-2. 「有期雇用契約」「無期雇用契約」のいずれかを選択する
雇用契約は、契約期間に応じて「有期雇用契約」と「無期雇用契約」の2種類に分類されます。
正社員の場合は原則として無期雇用契約が適用されますが、パートタイマーの場合、有期雇用契約と無期雇用契約のいずれかを選択することが可能です。
「有期雇用契約」とは
有期雇用契約とは、あらかじめ契約で定められた期間に限って雇用契約を締結することで、主に、臨時で雇われたパートタイマーやアルバイト、契約社員などに適用されます。
有期雇用契約の期間は、原則として3年(専門知識を持つ者や60歳以上などは例外的に5年)を上限としており、締結する際の雇用契約書に「労働契約の期間」「契約更新の有無」「更新する場合の基準」について明記する必要があります。
例えば「雇用期間の定めあり(2023/06/01~2023/07/31)」のように具体的な期間を記載します。契約更新がある場合はどのような条件で無期雇用転換の判断をおこなうかなどを雇用契約書に記載します。
また、雇用契約を3回以上更新している、あるいは雇用期間が1年を超えている従業員の雇用契約を更新しない場合は、30日前までに通知する必要があります。
契約期間満了後、契約を更新するかどうかは雇用主の判断によります。しかし、契約更新に関してはあらかじめ明確な基準やルールを設けておかないと、労働者側から不法な契約打ち切りを受けたとして訴えられる可能性があるため注意しましょう。
「無期雇用契約」とは
無期雇用契約とは、労働者と期間の定めなく雇用契約を締結することで、労働者からの申し出が無い場合は、原則として定年まで雇用する契約です。
パートタイマーに長期間の間継続して仕事に従事してもらう場合は、無期の雇用契約を結ぶことになるでしょう。
ちなみに、雇用契約の期間を明記せずに雇用契約を締結した場合は無期雇用契約扱いとなります。その場合は、正当な理由や労働者からの申し出がない限り、労働者との雇用契約を終了できなくなるため要注意です。
臨時的な雇用ではなく、長期的に労働に従事してほしい場合は、契約更新の必要がない無期雇用契約を締結するか、あるいは雇用契約書に「期間満了時に異議がない場合、自動的に契約が更新される」といった事項を盛り込んでおくと、契約更新の手間を省けます。
4-3. 勤務時間を正しく記載する
雇用契約書に記載する内容としては、労働者の「勤務時間」に関する内容も挙げられます。
毎日決まった時間帯で勤務する正社員とは異なり、パートタイマーは勤務する時間帯や日数にばらつきが生じます。そのため、雇用契約書に記載する場合は注意が必要です。
勤務時間が定まっている場合は、「始業時刻」「終業時刻」「休憩時間」を記載すれば良いため、1パターンのみ記載する形になります。
しかし、シフト制などで勤務時間が定まっていない場合は、パートタイマーが1週間に何日程度・合計で何時間程度働くか示した上で、シフトの時間帯を何パターンかに分けて記載しなくてはなりません。
関連記事:パート社員の雇用契約書で勤務時間を記載するときの注意点
4-4. 正社員との不当な格差が生じていないか確認する
パートタイマーと正社員の不当な格差を是正するために、国は各種法制度の整備を実施しています。
パートタイマーを雇用する場合は、「労働基準法」「パートタイム・有期雇用労働法」といった法律を遵守するとともに、自社で設定している就業規則に記載されている労働条件を下回らないように注意してください。
特に、賃金や昇給などを決めるときは、正社員との間に不当な格差が生じていないかどうかにも十分配慮しなければなりません。
「就業規則では全ての社員に手当を支給することが記載されているのに、パートタイマーには支給されないように雇用契約を結んでいる」「就業規則には昇給の基準が記載されているのに、パートタイマーは昇給がない」といったケースは不合理な待遇差と言われかねません。
また、パートタイマーの賃金が最低賃金を下回っていないことも確認しておきましょう。
4-5. 有給休暇について記載する
有給休暇というのは、雇用形態に関係なく付与することが義務付けられています。また、年に10日以上の有給休暇が付与される従業員には、年5日の有給休暇を取得させることも義務となっています。
ただし、有給休暇はすべての従業員に自動的に与えられるものではなく、労働基準法で定められた付与条件があります。
- 入社をして6か月経った時点を初回付日日とし、1年経過するごとに付与される
- 所定労働日のうち80%以上の出勤率がある
これらの条件を満たしていない場合は、正社員でもパートでも有給休暇は付与されません。
この条件を記載しておくことで、従業員が自分で有給休暇付与対象かを確認することができます。
5. 雇用契約書のサイン後にパートが辞退・退職したら?

雇用契約書を取り交わした後に、パートタイム労働者から働くことを辞退された場合、どのような対応を取るべきでしょうか?
まず、雇用契約書を取り交わしている段階で、雇用契約が成立しています。パートタイマーという雇用形態の場合でも試用期間を設ける場合もありますが、雇用契約書を取り交わしたタイミングで雇用契約が成立していることに変わりはありません。試用期間であっても雇用契約が結ばれている状態ということになります。
ここでのポイントは、「契約期間」の定めの有無です。
無期雇用の場合、民法の定めにより従業員が2週間に退職の意思を申し出た場合、企業側が応じていなくとも2週間が経過したら雇用契約が終了します。
一方で有期雇用の場合は、民法の定めにより原則契約期間中の退職が難しく、従業員にやむを得ない事由がない限り認められない、と扱われています。
「やむを得ない事由」の詳細はケースバイケースであるため、無用なトラブルを招かないためにも、弁護士や社労士などの専門家に相談することをおすすめします。
なお、パートタイム労働者が退職する際は、法的には退職届を提出しなくてもよいとされています。社内の手続き上退職届が必要な場合は、その旨を雇用契約書や就業規則などに明示しておくようにしましょう。
6. パートタイマーに対しても雇用契約書を作成してトラブルを防ごう
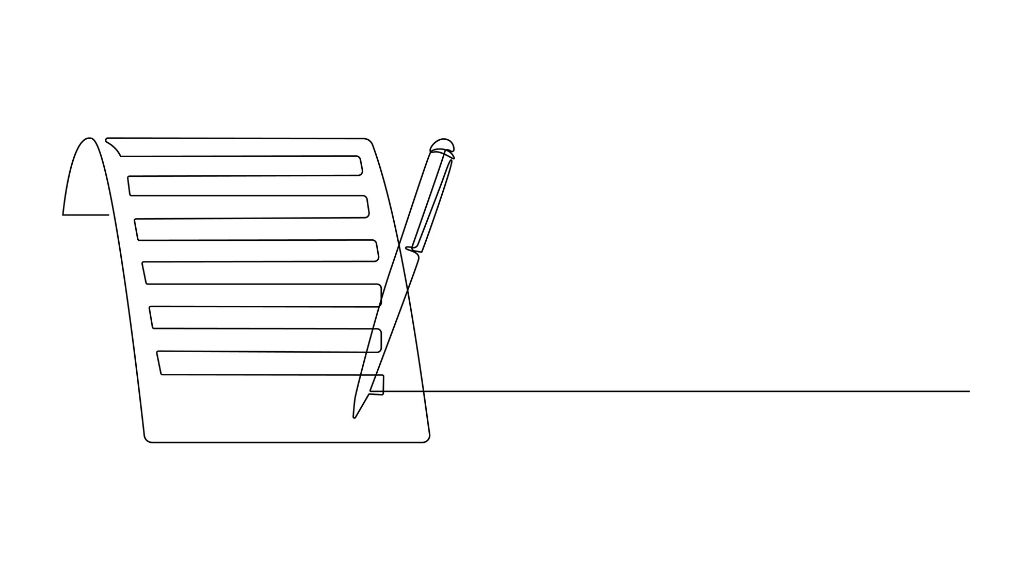
パートタイマーの労働条件は、正社員のそれとは異なるため、雇用契約を締結する際はパートタイマー専用の雇用契約書を発行する必要があります。労働条件を書面で明示するのはもちろん、正社員との間に不当な格差が生じていないかどうかにも十分配慮しながら、作成するようにしましょう。
ただし、パート・アルバイトの従業員が多い企業では、採用するたびに雇用契約書や労働条件通知書、入社書類などを準備するのに手間がかかってしまい業務負担が大きくなるかもしれません。
しかし、2019年の法改正で労働条件通知書のペーパーレス化が認められたことにより、パート・アルバイト従業員の入社にかかる業務や手続きの工数を削減できる雇用契約書の電子化が注目を集めています。興味のある方は、以下の記事で詳しく解説しているためチェックしてみてください。
関連記事:雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?
きちんとした雇用契約書を作成しておけば、労働者との間のトラブルを未然に防ぐことができるため、パートタイマーを採用する際は不備のない雇用契約書を用意しておきましょう。
関連記事:正社員雇用で必須の雇用契約書の作成方法を分かりやすく解説
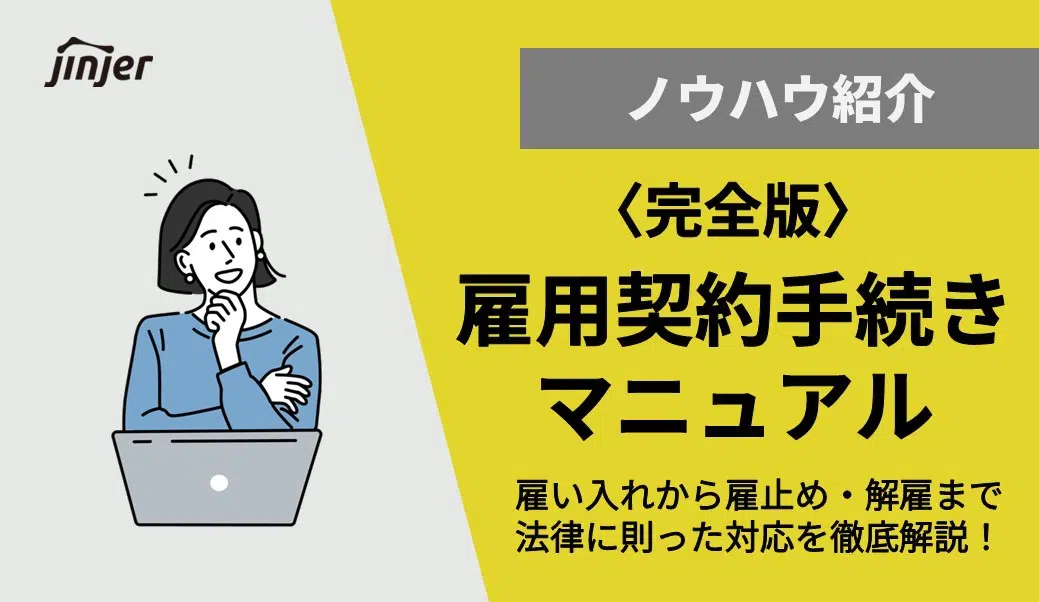
「長年この方法でやってきたから大丈夫」と思っていても、気づかぬうちに法改正や判例の変更により、自社の雇用契約がリスクを抱えているケースがあります。
従業員との無用なトラブルを避けるためにも、一度立ち止まって自社の対応を見直しませんか?
◆貴社の対応は万全ですか?セルフチェックリスト
- □ 労働条件通知書の「絶対的明示事項」を全て記載できているか
- □ 有期契約社員への「無期転換申込機会」の明示を忘れていないか
- □ 解雇予告のルールや、解雇が制限されるケースを正しく理解しているか
- □ 口頭での約束など、後にトラブルの火種となりうる慣行はないか
一つでも不安な項目があれば、正しい手続きの参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
雇用契約書の関連記事
-

雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや作成時の注意点を解説!
人事・労務管理公開日:2023.06.01更新日:2025.06.09
-

雇用契約書と労働条件通知書の兼用は可能?メリットや作成方法を解説
人事・労務管理公開日:2020.12.07更新日:2025.12.24
-

有期雇用契約書に正社員登用についての条件記載は必須?作成ポイントも解説!
人事・労務管理公開日:2020.12.07更新日:2025.12.24