給与計算のミスを防止する5つの施策を原因別に解説
更新日: 2025.8.28 公開日: 2020.12.14 jinjer Blog 編集部

給与計算では、極力ミスを防ぐ必要があります。しかし人間にミスはつきものです。本記事では、給与計算で起こりやすいミスとその原因別に5つの防止策を紹介します。
ミスの原因を理解したうえで防止策を講じることで、ミスが起こりにくい体制やフローを作りましょう。
【給与計算のやり方について解説はコチラ▶【図解】給与計算ガイド!例を用いて給与計算のやり方を徹底解説!】
【給与計算業務のまとめはコチラ▶給与計算とは?計算方法や業務上のリスク、効率化について徹底解説】
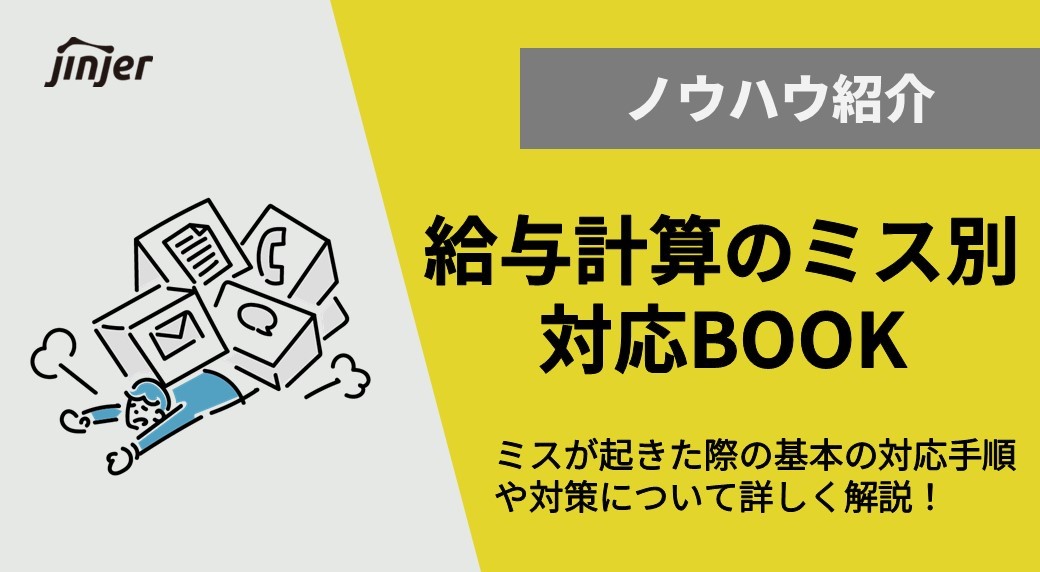
給与計算は、従業員との信頼関係に直結するため、本来絶対にミスがあってはならない業務ですが、計算ミスや更新漏れ、ヒューマンエラーが発生しやすいのも事実です。
当サイトでは、万が一ミスが発覚した場合に役立つ、ミス別に対応手順を解説した資料を無料配布しています。
資料では、ミス発覚時に参考になる基本の対応手順から、ミスを未然に防ぐための「起こりやすいミス」や「そもそも給与計算のミスを減らす方法」をわかりやすく解説しています。
◆この資料がおすすめできる方
・給与計算でミスが頻発していてお困りの方
・ミスをしないために、給与計算業務のチェックリストがほしい方
・根本的に給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
いずれかに当てはまる担当者の方は、ぜひ「給与計算のミス別対応BOOK」をダウンロードの上、日々の実務にお役立てください。
1. 給与計算でよくあるミス
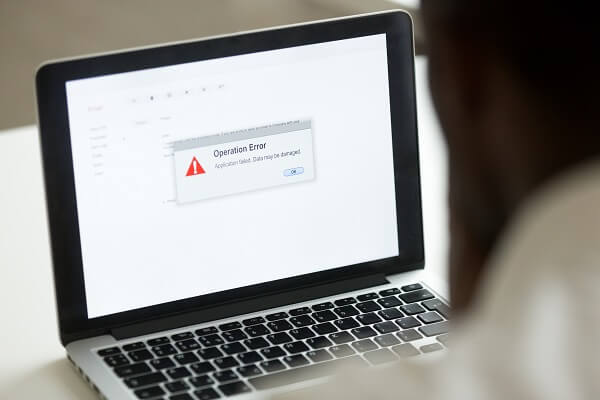
給与計算でどのようなミスが起こりやすいのかを知らなければ、注意するべき点やミスを防止するための対策はできません。給与計算で起こりやすいミスについて説明します。
1-1. 保険料率の改定を反映し忘れる
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)料率や労働保険(雇用保険、労災保険)料率と住民税は、毎年改定されます。改定されることを知らない、あるいは変わると知っていても変更月を忘れるなどのミスが起こりがちです。
健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険の4つの保険料は企業と従業員の2者が分担して納めます。一方で、労災保険は企業が全額納めます。
また、社会保険は毎月、労働保険は年に1回の支払いとなります。
従業員と企業が、それぞれどのような割合でいついくら支払うのかを把握しないとミスに繋がってしまいます。
関連記事:社会保険料の徴収ミスの対処法は?会社負担の必要性や発生の原因、防止策を解説
1-2. 扶養変更・異動などの入力し忘れる
給与計算で特にミスが頻発するのが、扶養変更や異動などの変更があった場合です。
扶養変更として考えられるケースは、従業員に新たな家族が増えたり、従業員が扶養している家族が就職し扶養対象人数が変更になったりした、などが考えられます。異動の場合は、役職や職務の変更による手当の変更だけでなく、就業場所の変更による通勤手当や、会社によっては地域手当を付与する場合もあります。
これらは従業員一人一人で適用される手当も額も異なるため、変更を把握していないことによる変更となった金額の入力し忘れなどのミスが起こりやすくなります。
1-3. 年齢で追加される保険料を忘れる
介護保険料や雇用保険料は、開始や終了が年齢により決まっており、給与計算でミスをしやすい項目です。
介護保険料は、納付開始となる年齢と、納付終了となる年齢があります。
雇用保険料は、以前は納付終了となる年齢がありましたが法改正によって年齢による制限は撤廃されました。
また、該当年齢に達しているかどうかは、単純に誕生日を迎えたから、ではなく、細かい条件があります。
従業員ごとの生年月日を把握しなければならない点や、介護保険と雇用保険でルールが異なる点など、複数の要因が絡み合うことで混乱を招き、ミスが起こりやすいポイントです。
1-4. 月額変更届の届出を忘れる
昇給があったり、雇用形態が変わったりした場合に、標準報酬月額が大きく変わることがあります。通常、標準報酬月額はその年の4~6月の給与で算出され、算出された金額が同年の9月から翌年の8月まで変わりません。しかし、以下のすべてに当てはまるときは随時改定の手続きが必要です。
- 固定的賃金の変更があった
- それまでの標準報酬月額と変動月以前の3ヵ月間の標準報酬月額に2等級以上の差ができた
- 変動月以前の3ヵ月間の支払基礎日数が17日を超える
上記に当てはまる場合に「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(月額変更届)」の届出を忘れてしまうと、正しい保険料を徴収できません。
1-5. 日割り計算を間違える
月の途中で入職・退職した場合や、休職した場合には、給与の日割り計算が必要です。日割り計算では、除外する手当を間違えるなどが原因で計算ミスが起こりやすくなります。
日割りの計算は細かく複雑になりがちであるため、アナログな方法だと間違いが発生しやすいです。
日割り計算をしなければならないケースが多い場合や、イレギュラーな対応にとられる時間を減らしたい場合は、給与計算システムなどを活用するとよいでしょう。給与計算システムなら日割りの条件を設定することで、自動的に計算させることも可能になります。
2. 給与計算の入力ミスを減らす5つの方法

ミスの原因がわかれば気を付けるべき点が分かり、防止のための対策ができます。以下の5つの原因に対する防止策をそれぞれ解説します。
- 保険料率の改定把握には年間スケジュールを作成
- 扶養変更・異動などの入力忘れを防止するにはダブルチェック
- 控除項目の変更忘れ防止にはチェックリストを活用
- 月額変更届の届出忘れを防ぐためにマニュアルを作成
- 日割り計算を間違えの防止には給与計算システムを導入
2-1. 保険料率の改定把握には年間スケジュールを作成
保険料率は毎年決まった月に改定されます。年間スケジュールを作成することで改定月を把握し、ミスを防止しましょう。各保険料と税金の改定月は以下の通りです。
3月:健康保険料率、介護保険料率(4月納付分)
4月:雇用保険料率
6月:住民税額
この他に、昇給月など給与計算にかかわる社内のスケジュールも合わせて記載しておきましょう。特に、経験年数の浅い社員がいる場合には、スケジュールを視覚化しておくとミスの防止に繋がります。
【社会保険料と給与計算について詳しくはコチラ▶給与計算で社会保険料を算出する方法を分かりやすく解説】
保険料と税金の他にも、昇給月など給与計算にかかわる社内のスケジュールも合わせて記載しておくと1つの資料で給与計算に関するスケジュールを把握できるためおすすめです。
特に、経験年数の浅い社員がいる場合には、スケジュールを視覚化しておくことでミスの防止に繋がります。
【給与計算の流れと年間スケジュールはコチラ▶給与計算業務の流れ|月間と年間のスケジュールも紹介!】
2-2. 扶養変更・異動などの入力忘れを防止するにはダブルチェック
とくに注意したいのが、扶養人数や異動などで発生した変更事項の入力忘れや入力ミスです。
それを防ぐには、入力後のダブルチェック、場合によってはトリプルチェックが有効です。一人がミスをしても、別の目で確認することでミスを見逃す可能性を低くすることができます。
従業員から変更の届出があった場合や、変更事項を入力するときは必ず複数人でチェックする体制を作りましょう。
また、従業員や担当者がするべき報告を忘れないように、変更が発生しやすい時期の少し前にアナウンスをすることも大切です。
【給与計算のダブルチェックを強化する方法はコチラ▶給与計算におけるダブルチェックの重要性と精度を上げる方法】
2-3. 控除項目の変更忘れ防止にはチェックリストを活用
介護保険料は40歳から開始され、65歳以上の従業員では徴収が終了となります。
また、雇用保険料に関しては、2020年度より65歳以上でも納付が必要になりました。
介護保険料については誕生月の前日から適用、雇用保険料は4月1日時点での年齢で適用です。その年に適用となる人と適用となる月を抽出し、事前にチェックリストを作成しておくと良いでしょう。
【65歳以上でも雇用保険料の納付が必要になりました▶【2020年4月改正】65歳以上の雇用保険料に関する給与計算ルール】
2-4. 月額変更届の届出忘れを防ぐためにマニュアルを作成
月額変更届の届出忘れを防止するために、手順をマニュアル化しておくと経験の少ない社員でも間違えにくくなります。マニュアルどおりにおこなうことで、手順を飛ばしてしまうミスも防げます。
マニュアルを作成する手間はかかってしまいますが、今後慣れていない人がミスし、それに対応する時間を考えると作成した置いた方が賢明です。
注意点や届け出をすべきタイミングなども記載し、周知しておくと効果的です。
2-5. 日割り計算を間違えの防止には給与計算システムを導入
日割り計算などを手計算ですると、どうしてもミスを犯しやすくなります。また、常に法改正されていないかアンテナを張りながら正しい給与を支払う必要があります。変更後の給与支払いのタイミングで、税率の変更を忘れてしまい支払額に間違いが生じるなど、単純な計算ミス以外にも多くのリスクをはらんでいます。
システムを導入することで、日割り計算や時給計算の単純計算のミスが低減し、税率の変更忘れのミスも自動で更新されるためなくなります。
「給与計算システムで業務がどれだけ楽になり、ミスが減らせるのか知りたい」という方にむけ、当サイトでは、給与計算システムジンジャー給与を例に給与計算システムのサービス内容が分かる資料を無料で配布しております。
システム導入によってミスを減らしたいと考えている方は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
3. 給与計算ミスがおきるとどうなるか
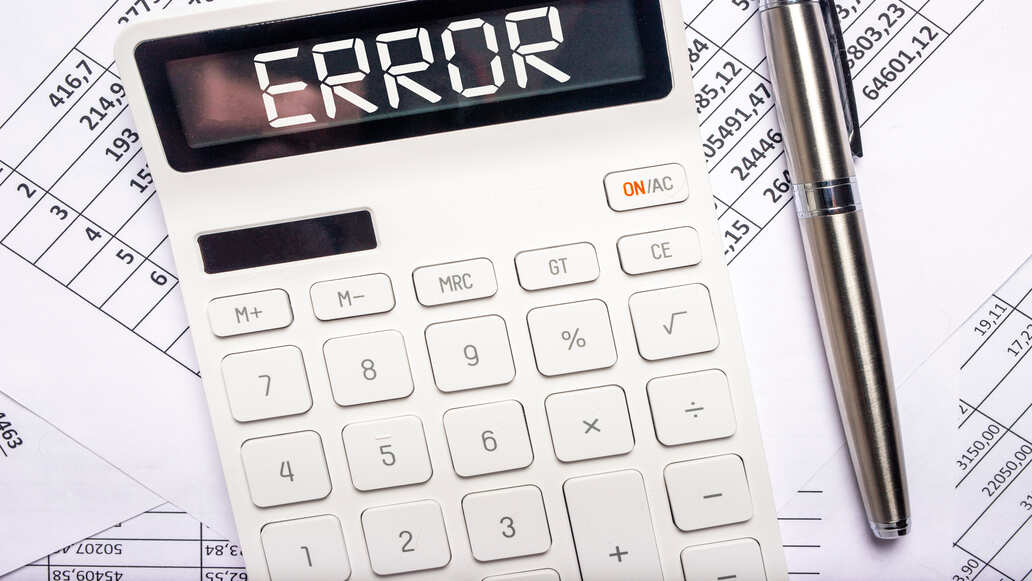
毎月同じ業務をしていると集中力や危機感が低下し、ミスに繋がってしまうかもしれません。
緊張感を持続させるためにも、給与計算ミスが起こってしまった時、どのようなリスクがあるか、責任の所在はどうなるのかを知っておきましょう。
3-1. 従業員や社外からの信頼を失うことにつながる
たとえ故意でなかったとしても、重要な給与の計算ミスは社従業員からの信頼を落とすことにつながるかもしれません。
給与計算をミスしたのはいち従業員に対してかもしれませんが、受け取る側からは会社のミスと見なされ、会社の責任と捉えられてしまいます。
また、給与ミスが長期間放置された場合や、多人数に及んだ場合などは、大きなトラブルに発展して社外にも伝わる恐れがあります。
「問題を起こした企業」として認識されてしまうと、社外からの信頼にも影を落とすことになるでしょう。
企業への信頼性が落ちてしまうと属している従業員のモチベーションや忠誠心の低下、取引先からの印象の低下が懸念されます。ミスが発生した場合は、速やかに謝罪・対処し、適切な補償や修正をおこないましょう。
3-2. 「賃金支払いの5原則」に違反することになる
法律の観点では、もし給与計算のミスにより給与支払いの遅延が起きた場合、「賃金支払いの5原則」に抵触し違法となります。
給与計算のミスにより、従業員に対して正当な給与が支払われない場合、企業は従業員に対して不利益をもたらすことになります。従業員は正当な給与を受け取る権利があり、企業はその責任を負うことになります。
ミスにすぐに気付いて対応できれば法的な問題を問われることはほとんどありません。
しかし、従業員側が気づいて労働基準監督署などに相談してしまった場合は、問題が大きくなりやすいです。法律を遵守するためにも、給与計算のミスはあってはなりません。
4. 給与計算はミスがなくて当たり前!システムを活用してミスをなくそう

給与計算でミスをすることは、絶対に避けなくてはいけません。しかし、人の手が入る以上、ミスを防ぐことは難しいのが現状です。そこで活用したいのが給与計算システムです。ミスをしやすい計算も、システムが自動で算出してくれます。また、人事管理システムと連携させることで昇給時の入力忘れを防ぐことが可能です。
ジンジャーでは、給与計算システムの他に人事管理システムを用意しています。それぞれのシステムを連携することも可能なため、ミス防止にも役立つでしょう。
【給与計算でミスがあった際の対応を知りたい方はコチラ▶給与計算でミスしたときの対処法は?要因とその防止策もご紹介】
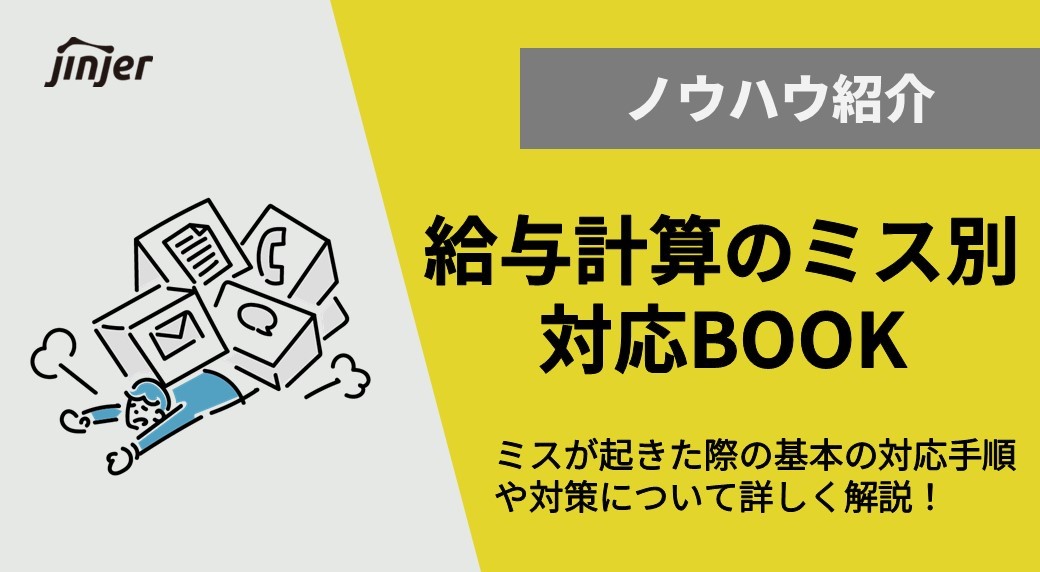
給与計算は、従業員との信頼関係に直結するため、本来絶対にミスがあってはならない業務ですが、計算ミスや更新漏れ、ヒューマンエラーが発生しやすいのも事実です。
当サイトでは、万が一ミスが発覚した場合に役立つ、ミス別に対応手順を解説した資料を無料配布しています。
資料では、ミス発覚時に参考になる基本の対応手順から、ミスを未然に防ぐための「起こりやすいミス」や「そもそも給与計算のミスを減らす方法」をわかりやすく解説しています。
◆この資料がおすすめできる方
・給与計算でミスが頻発していてお困りの方
・ミスをしないために、給与計算業務のチェックリストがほしい方
・根本的に給与計算のミスを減らす方法を知りたい方
いずれかに当てはまる担当者の方は、ぜひ「給与計算のミス別対応BOOK」をダウンロードの上、日々の実務にお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
業務のお悩み解決法の関連記事
-


人件費削減とは?人件費削減のメリット・デメリットも網羅的に解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
-


経費削減とは?今すぐ実践できる経費削減とその注意点を解説
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
-


人件費削減の方法とは?具体的な方法や失敗しないためのポイント
経費管理公開日:2022.03.03更新日:2025.06.18
給与計算の関連記事
-


雇用保険の休職手当とは?受給条件や申請方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.06.18更新日:2025.08.28
-


パート従業員にも休職手当を支給できる?支給条件や注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.17更新日:2025.08.28
-


休職手当はいくら支払う?金額や支給条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.06.16更新日:2025.08.28






















