所得税とは?源泉所得税や定額減税など複雑な処理を詳しく解説

所得税を計算する上で所得税の基礎的知識は必須です。所得税にはどんな種類があり、どんな方法によって納税するのか、事前にしっかりおさえておきましょう。
本記事では、所得税の種類や計算方法、納税の仕方や確定申告が必要となるケースなどを詳しく解説します。
目次

労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな担当者の方には、人事労務から勤怠管理までが一つになったシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
-
勤怠データをワンクリックで取り込めるため、勤怠の締めから給与計算までをスムーズに自動化できる
-
昇格や異動に伴う給与体系の変更も、人事情報と連携しているため設定漏れを防ぐことができる
-
Web給与明細で印刷・封入コストがゼロ・ 発行ボタン一つで、全従業員へ給与明細を配布可能
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
1. 所得税とは


まずは所得や所得税の考え方と、「申告所得税」「源泉所得税」の違いなどについて確認していきましょう。
1-1. 個人の所得に対して課される税金
所得税とは、所得税法に定められているとおり、会社から支給される給料や個人で商売をして儲けた利益など、個人の所得に対して課せられる税金のことです。
1年間(1月1日〜12月31日)の総所得から、必要経費や所定の控除額を引いた金額に、所得税率をかけて算出された金額を確定申告で納税します。
なお、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの期間は、東日本大震災の復興支援の財源となる「復興特別所得税」を所得税と合わせて納税する必要があるため、注意が必要です。
所得には会社から支給される給与の他にも種類があります。所得の種類によって、計算の仕方や控除の有無、納税の仕方が変わってくるため、事前に押さえておきましょう。
関連記事:所得税と住民税の違いは?高いのは?計算方法の違いについても解説
参考:個人の方に係る復興特別所得税のあらまし|国税庁
1-2. 「申告所得税」と「源泉所得税」
申告所得税は、主に個人事業主やフリーランスなど、自営業や副業などの所得がある個人が自ら申告し納付する税金です。
これに対して源泉所得税は、従業員の代わりに企業(雇用主)が源泉徴収制度に基づいて給与から所得税を天引きし、企業(雇用主)が代わりに所定の税務署へ納付する税金です。
一般的に、企業に所属する従業員は源泉所得税の方法で所得税を納税するため、従業員は申告所得税の方法で納税する必要はありません。
ただし、従業員が他の収入源(副業や投資など)を持つ場合や、所得税の調整が必要な場合には、従業員へ申告所得税の方法で自ら申告してもらう必要があります。
1-3. 所得の種類
所得は税制上以下の10種類に分けて所得税を計算します。基本的には所得の種類ごとに所得額を算出してから合算する総合課税となっていますが、一部は総合課税には含めずに計算する分離課税となっています。
| 利子所得 | 分離課税 | 預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金などが該当します。利子が発生した際に所得税が源泉徴収されるため、確定申告は不要です。 |
| 配当所得 | 総合課税 | 株式の配当金や株式投資信託などの収益分配金などが該当します。 |
| 不動産所得 | 総合課税 | 家賃や駐車場代といった不動産の権利から生ずる所得、または船舶・航空機の貸付による所得が該当します。 |
| 事業所得 | 総合課税 | 農業、漁業、サービス業など継続しておこなわれる事業から生じた利益などが事業所得です。個人事業主やフリーランスの方の収入はこれに該当します。 |
| 給与所得 | 総合課税 | 公務員や会社員、パート・アルバイトの給料や賞与、役員報酬などの所得が該当します。通勤費や旅費交通費は規定の限度額内であれば非課税となります。 |
退職所得 |
分離課税 | 退職金や役員退職金、企業年金の退職一時金などが該当します。確定給付企業年金法や確定拠出年金法に基づいて支払われる一時金も含まれます。 |
| 山林所得 | 分離課税 | 山林を伐採して売却または譲渡によって得る所得です。ただし、所有して5年以内に伐採や譲渡で得た所得は事業所得や雑所得となります。 |
| 譲渡所得 | 分離課税または総合課税 | 不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡したことによって生じる所得です。ただし、事業用の商品や山林の譲渡は譲渡所得に含まれません。土地や建物、株式などの譲渡は分離課税となり、その他の譲渡は総合課税となります。 |
| 一時所得 | 総合課税 | 保険の満期保険金や解約返戻金など、営利目的以外の行為によって生じた所得が該当します。 |
| 雑所得 | 総合課税 | いずれの所得にも該当しないものが雑所得となります。公的年金や原稿料、講演料、デザイン料などが該当します。 |
関連記事:賞与から引かれる所得税の基礎知識と計算方法について解説
2. 2024年におこなわれた定額減税とは
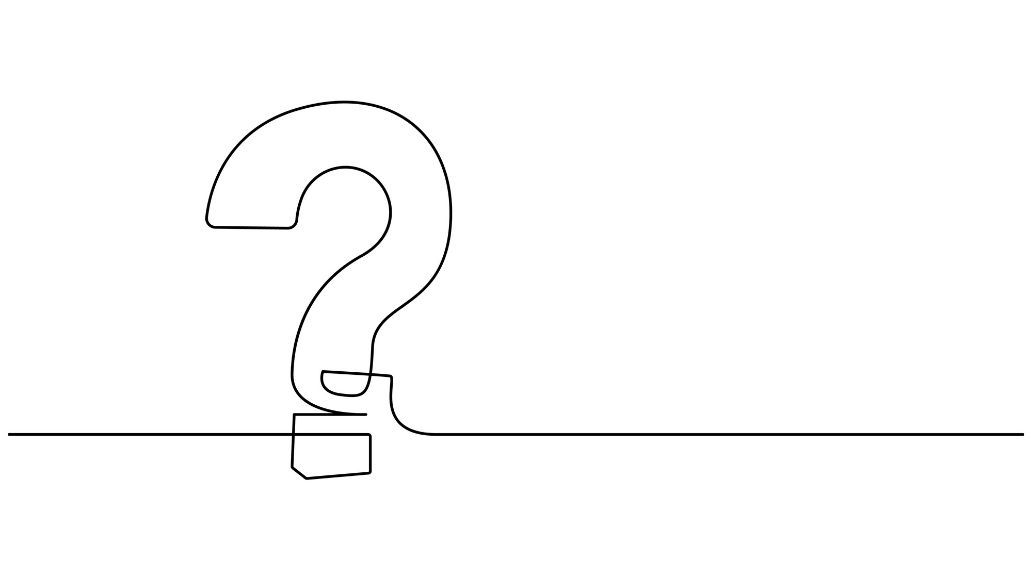
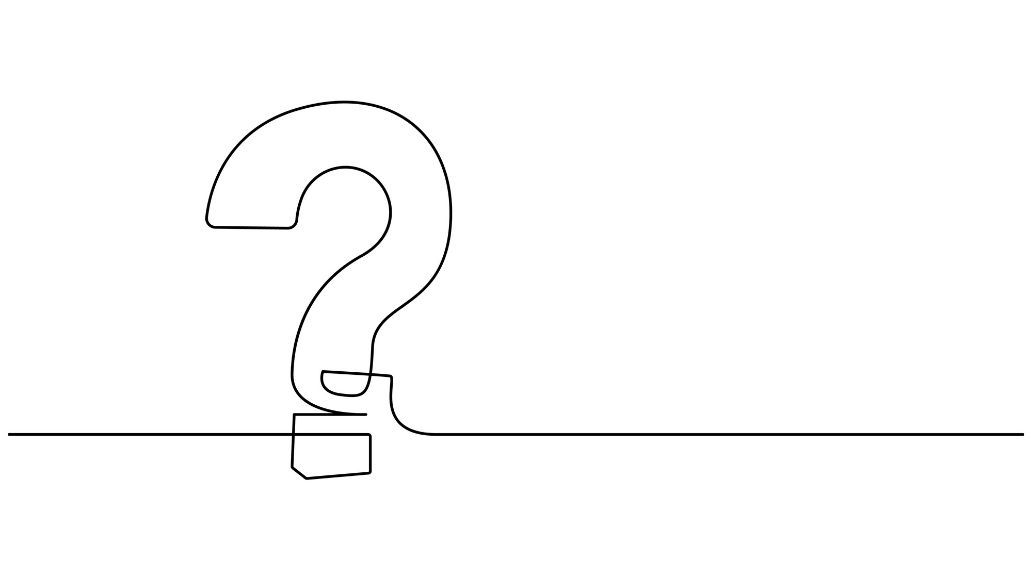
所得税の計算をする場合、2024年に実施された定額減税についても知っておかなければなりません。どのような制度なのか、対象者や減税金額について確認しておきましょう。
2-1. 所得税と住民税が控除される制度
定額減税とは、所得税と住民税から一定額を減税する制度です。国民の生活負担を軽減することが目的の政策であり、2024年から始まっています。
2024年の6月からスタートしている制度ですが、6月で控除が終わらない場合は2024年7月以降も減税が続くシステムです。
定額減税への対応は、企業側が給与計算をする際に追加でおこなわなくてはなりません。今後も実施される可能性があるため、担当者は定額減税のシステムや対象者、計算方法などを十分に理解しておく必要があります。
2-2. 定額減税の対象者
定額減税は無条件ですべての人が対象になるものではありません。所得税と住民税に分けて、定額減税の対象者になる条件を知っておきましょう。
所得税の定額減税対象者
所得税の定額減税が適用される条件は以下の通りです。
| 所得税 | 対象納税者 | ・2024年分の合計所得金額が1,805万円以下 ・国内居住者 ※収入が給与のみの場合は2,000万円以下 ※所得金額調整控除の適用を受けている場合は2,015万円以下 |
| 同一生計配偶者 | ・納税者と生計が同一で、2024年分の合計所得金額が48万円以下の配偶者 ・国内居住者 ※配偶者の収入が給与のみの場合は103万円以下 | |
| 扶養親族 | ・納税者と生計が同一で、2024年分の合計所得金額が48万円以下の親族 ・扶養控除申告書に記載された「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」 ・国内居住者 ※扶養親族の収入が給与のみの場合は103万円以下 |
住民税の定額減税対象者
住民税の定額減税が適用される条件は以下の通りです。
| 住民税 | 対象納税者 | ・2023年分の合計所得金額が1,805万円以下 ・国内居住者かつ2023年分の住民税の課税対象者 |
| 控除対象配偶者 | ・納税者と生計が同一で、2023年の合計所得金額が48万円以下の配偶者 ・対象納税者の2023年の合計所得金額が1,000万円以下 ・国内居住者 ※配偶者の収入が給与のみの場合は103万円以下 | |
| 扶養親族 | ・納税者と生計が同一で、2023年の合計所得金額が48万円以下の親族 ・国内居住者(非居住者は対象外) ※扶養親族の収入が給与のみの場合は103万円以下 |
2-3. 定額減税額
定額減税額は以下のように定められています。
所得税…対象者1人につき3万円
住民税…対象者1人につき1万円
夫婦と子供が2人いる世帯の場合は、以下のような計算になります。
所得税:本人(3万円)+同一生計配偶者(3万円)+扶養親族2人(6万円)=12万円
住民税:本人(1万円)+同一生計配偶者(1万円)+扶養親族2人(2万円)=4万円
ただし、定額減税制度は減税額や対象者になる条件などが変更される可能性があります。定額減税制度に変化があった場合は、必ず最新の情報で対応できるようにしておきましょう。
給与計算ソフトを使う場合は自動で最新の税制に対応できるものがおすすめです。自動で更新されるシステムであれば、設定の変更やその都度の対応も必要ありません。
関連記事:【2024年6月】定額減税とは?対象者や減税額・給付金をわかりやすく解説
3. 所得税の税率はどのように決まるのか


所得税は所得がいくらを超えるとかかるのか、決まり方や税率について確認しておきましょう。
3-1. 所得税はいくらからかかる?
所得税が発生する条件は年収103万円を超えたタイミングです。給与所得の控除の最低額である55万円、基礎控除の48万円の合計が103万円になるため、雇用形態に関わらず年収が103万円を超えると所得税が発生します。
例えば、年収が150万円であれば、103万円を超えた47万円に所得税がかかります。先述のとおり課税所得金額が194万9,000円までであれば税率は5%です。そのため、超えた47万円に5%を乗じた2万3,500円が所得税です。さらに復興特別税として令和19年度までは所得税額に2.1%がかかります。
なお、学生の場合は勤労学生控除が適用されます。そのため、学生アルバイトは年収103万円でなく、年収が130万円を超えると所得税が発生します。
3-2. 所得税は超過累進税率になっている
所得税の税率は所得金額に応じて段階的に変わる超過累進税率となっており、所得金額が大きくなるほど税率も高くなります。税率は下記の所得税率計算表をご覧ください。
なお、復興特別所得税の税率に関しては、一律で2.1%となっています。
【所得税率計算表】
|
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000円から1,949,000円まで |
5% |
0円 |
|
1,950,000円から3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
|
3,300,000円から6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
|
6,950,000円から8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
|
9,000,000円から17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
|
18,000,000円から39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
|
40,000,000円以上 |
45% |
4,796,000円 |
所得税の税率は今後改定される場合があるため、確定申告等で所得税を計算する必要がある際は、国税庁のホームページなどで最新の税率を確認するようにしましょう。
関連記事:所得税率は所得金額で変わる!税率改定の影響や注意すべきポイント
関連記事:所得税における累進課税制度とは?基礎知識やメリット・デメリットを解説
関連記事:所得税は年収いくらから?年収103万を超える場合や年収の壁について解説
4. 所得税の計算方法


所得税の計算は次に紹介する3つのステップを踏んで算出します。所得税を計算ツールはありますが、確定申告をスムーズに手続きするためにも、自分でも計算の手順についてしっかりおさえておきましょう。
4-1. 所得金額を計算する
収入金額から必要経費(または所定の控除額)を差し引いて所得金額を計算します。
所得金額=収入金額-必要経費(または所定の控除額)
例えば、個人事業主やフリーランスの方は、売上にかかったコスト(売上原価や販売管理費など)を収入金額から引いて所得金額を算出します。
また、給与取得者は必要経費の代わりに給与所得控除を収入金額から引いて、所得金額を算出します。
4-2. 課税所得額を計算する
次に、課税所得額を算出します。所得金額から所得控除を差し引いて課税所得額を計算します。
課税所得額=所得金額-所得控除
所得控除には次のようなものがあります。
【所得控除の種類】
雑損控除/医療控除/社会保険料控除/小規模企業共済等掛金控除/生命保険料控除/地震保険料控除/寄付金控除/障害者控除/基礎控除/配偶者控除/配偶者特別控除/扶養控除/寡婦(寡夫)控除/ひとり親控除/勤労学生控除
関連記事:所得税における控除とは?控除の種類や所得控除を受ける方法を解説
関連記事:所得税における通勤手当の課税・非課税ルールとは?交通費のとの違いも解説
4-3. 所得税と復興特別所得税を計算する
課税所得額から前述の所得税速算表にある控除額を引いて所得税を算出します。税額控除がある場合は、所得税からさらに税額控除を引いた額が最終的な所得税額となります。
所得税=課税所得額×所得税率-速算表の控除額-税額控除
復興特別所得税=所得税×2.1%
税額控除の種類は以下の通りです。
【税額控除の種類】
配当控除/外国税額控除/住宅借入金等特別控除/住宅特定改修特別税額控除
所得税と復興特別所得税を合算した金額が納税する金額となります。
所得税などの税金の計算は人為ミスが起きやすいため、ダブルチェックを忘れずにおこなったり、システムを導入したりするなど、極力ミスを減らす工夫が求められます。
当サイトでは、本章で解説した税金の計算方法や税金計算時に気を付けるべきポイントを解説した資料を無料で配布しております。
そのほかにも、住民税や所得税の違いなどの基礎知識もまとめてあるため、税金計算に関していつでも確認できる資料が気になるご担当者様は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:所得税とは?|源泉所得税の計算方法や税額表の見方を解説
関連記事:所得税の計算方法は?計算を効率良く行う方法や年収が変わった場合について
関連記事:所得税が毎月変わる理由とチェックするべき項目は?標準報酬月額も解説
5. 所得税を納税する方法


所得税は次の5通りの方法によって納税することが可能です。税務署や銀行の窓口に行かずとも、会社や自宅に居ながら納税することもできるため、期日までにいずれかの方法によって忘れずに納税しましょう。
関連記事:所得税納付書の入手方法は?所得税納付書の種類や提出方法・期限を解説
関連記事:所得税徴収高計算書とは?基礎知識や記載するときの注意点を解説
関連記事:所得税の納付方法の種類や支払い期限・選び方を解説
5-1. 振替納税
納税者の預貯金口座から引落しによって納税する方法で、所得税の納付期日から約1ヵ月後に指定の口座から引落しとなります。
振替納税を利用するには、所得税の納付期日までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所轄の税務署、または引落し口座の金融機関に提出しなくてはなりません。
一度手続きしてしまえば、翌年以降は継続して口座から引落しによって納税できるため、面倒な手間は最初だけです。
令和3年1月から、個人の方を対象にe-Taxから振替依頼書の記入や押印なしで簡単に手続きが可能となっています。
5-2. 電子納税
オンライン上で納税をおこなう方法で、「ダイレクト納付」と「インターネットバンキング納付」の2方式があります。
ダイレクト納付
事前にダイレクト納付の手続きを済ませておくことで、e-Tax上で所得税の申告手続きから納税までを一貫しておこなうことができます。
「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を所轄の税務署、または金融機関に提出してe-Taxと引落し口座を紐づけをすることで、利用することが可能です。
令和3年1月から振替納税と同様、個人の方を対象にe-Taxから記入や押印なしで簡単に手続きができます。
インターネットバンキング納付
e-taxで取得した納付区分番号(もしくは納付目的コード)を元に、インターネットバンキングまたはATMから支払う方法です。利用するには、e-Taxから電子申告後に納付情報データを送信して納付区分番号を取得する「登録方式」、または納付情報データを送信せずに自分で納付目的コードを作成する「入力方式」の2つの方法があります。
税金・各種支払サービスの「ペイジー」であれば、登録方式・入力方式どちらでも支払いが可能です。
5-3. クレジットカード納税
「国税クレジットカードお支払サイト」から、納税者の情報や納税金額、クレジットカード情報を入力して納税する方法です。クレジットカード納税に関しては事前に手続きが不要で、専用サイトから24時間いつでも支払することができます。
ただし、納税金額に応じて決済手数料が発生するため注意しましょう。クレジットカード納税であれば、分割払いやリボ払いが利用できます。
5-4. コンビニ納税
所得税額が30万円以下の場合は、コンビニでの納税が可能です。
国税庁のHP「確定申告書等作成コーナー」または「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」、e-TaxでQRコードを作成してスマートフォンなどに保存します。
コンビニのキオスク端末で作成したQRコードを読み取らせて納付書を印刷し、コンビニの窓口で支払います。
利用できるコンビニはローソンやナチュラルローソン、ミニストップの「Loppi」設置店、またはファミリーマートの「Famiポート」設置店に限ります。
5-5. 窓口納税
所轄の税務署や金融機関の窓口へ直接出向いて納税する方法です。
税務署または金融機関に備え付けの納付書に必要事項を記入して、窓口へ現金で支払いをします。
なお上述1〜4の方法では領収書が発行されないため、領収書が必要な方は窓口納税で支払わなければなりません。
5-6. 納税期日を過ぎた場合はどうなる?
納税期日を過ぎてしまった場合は、延滞日数に応じて延滞税が発生します。
納税期日の翌日から2ヵ月以内は、「年7.3%」または「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方を、2ヵ月を過ぎた場合は「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方で延滞税を支払わなくてはいけません。
また、確定申告自体の期日が過ぎてしまった場合は、50万円までは15%、50万円を超える分については20%の加算税がかかります。
確定申告も所得税の納税も、期日までに必ずおこなうようにしましょう。
6. 所得税と確定申告の関係


所得税と確定申告は非常に深い関係があります。会社側が個人の確定申告をすることはありませんが、従業員から聞かれた場合に答えられるように確定申告の基本と、確定申告が必要になる条件などを知っておきましょう。
6-1. 確定申告は所得税額を決めるための手続き
確定申告は、年間に所得がある場合におこなって所得税額を決定する手続きです。そのため、所得があった場合はおこなわなくてはなりませんが、所得より経費や控除額が上回る場合は確定申告は不要となります。
また、会社員のような給与所得者は、会社が源泉徴収によって代わりに所得税を納税しているため確定申告は不要です。しかし、一定の要件を満たさない場合には、給与所得者であっても確定申告をしなくてはなりません。
6-2. 確定申告が必要な人と不要な人がいる
前述したように、確定申告は特定の条件を満たしている場合は所得があっても必要ではありません。確定申告が必要な人と不要な人をそれぞれ確認しておきましょう。
確定申告が必要な人
確定申告が必要な人は、以下の通りです。
【事業所得のあるフリーランスや個人事業主の人】
企業には所属していないフリーランスや個人事業主の人は、個人で事業をおこなって得た収入が事業所得となります。
事業所得から必要経費や所得控除などを引いた際にプラスの金額となる場合は、確定申告をおこなわなくてはなりません。
【一定の要件を満たす会社員の人】
給与所得者の中でも、「年間の収入が2,000万円超」、「2ヵ所以上から給与の支給を受けている」、「20万円を超える別収入がある」といった要件のいずれかに該当する場合は、年末調整の対象外になるため個別に確定申告が必要となってきます。
【不動産や株取引で収入がある人】
家賃収入など不動産の貸与や譲渡によって不動産所得や譲渡所得を得ている人は、確定申告が必要です。
また、株取引で利益を得ている場合でも同様となります。
ただし、株取引に関しては、NISA口座を利用していれば120万円までの利益は確定申告が不要などの規定が設けられています。
【一定額を超える公的年金を受け取っている人】
公的年金受給者で源泉徴収がおこなわれている場合は、確定申告が不要です。
ただし、公的年金などの年間収入額が400万円を超える場合や、公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
確定申告が不要な人
確定申告が不要な人は、以下の通りです。
【年間の所得が48万円以下の人】
2020年の確定申告より基礎控除額が48万円に改定されました。
基礎控除とは、所得が一定額の範囲内であれば無条件で適用できる所得控除のひとつです。
事業所得などの年間の所得が48万円以下になるようであれば、確定申告は不要となります。
【会社で年末調整を受けている人】
年末調整とは、源泉徴収によって納税した所得税額と実際に支払われた給与に対する所得税額を比較して年末に過不足分を精算することです。
年末調整を受けている場合は、確定申告する必要はありません。
【公的年金で源泉徴収されている人】
前述でも触れましたが、公的年金受給者で年収が400万円未満であり、他の所得が20万円を超えておらず、源泉徴収によって支給される年金から所得税が引かれている人は確定申告が不要です。
【副業などの収入が20万円以下の人】
会社員の方などで副業の収入がある場合、20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
しかし、20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。
関連記事:2021年の所得税関連の税制改正を知ろう!確定申告や還付金について解説
関連記事:所得税のための年末調整とは?基礎知識や対象になる人・ならない人を解説
7. 所得税と源泉所得税の違いは?


所得税と源泉所得税は、どちらも「所得税」という名前がつくことから、しばしば混同されることがあります。しかし、給与計算や年末調整をする際には違いを知っておかなくてはなりません。
7-1. 納税方法が違う
所得税と源泉所得税はどちらも個人の所得に課せられる税ですが、両者の違いは納税方法です。
所得税は1年間の所得を確定申告し、その結果の納税額を納税する方法です。一方、源泉所得税は給与や報酬など一部の所得に対しての税金を支払者が本人に代わって納税します。
一般的に会社員は源泉所得税が給与から天引きされます。このように会社員は源泉徴収されるため、納税者の手間が省かれるでしょう。また、源泉所得税であれば国が税金を早期に確保できるという特徴もあります。
7-2. 年末調整で正確な徴収額が決定する
所得税は1年間の所得に対してかかるものです。そのため、会社員が毎月給与から天引きされている源泉所得税には、所得税の前払いのような性質があります。1年間の所得が正確にわかっていない状態で所得税を支払っている状態であるため、1年の所得にかかる所得税と、徴収済みの源泉所得税に差が生じることがあります。
このような源泉所得税と実際の所得税の間に発生する誤差を調整するのが「年末調整」です。年末調整によって、徴収済みの源泉所得税が多すぎる場合は払いすぎた分が還付され、少なすぎる場合は追加で支払いが発生します。
8. 所得税の基礎をしっかり押さえて期日までに正しく納税をおこなおう


税制上の所得には全部で10種類あり、中には個別に所得税計算をおこなわなくてはいけない所得もあるため、事前にしっかりおさえておきましょう。また、いくらからの年収で所得税が発生するのかも把握が必要です。
所得税の納付方法には、窓口納付以外にもオンラインを通じた納付方法がいくつか用意されています。窓口に行く時間がない場合は、オンライン納税を活用するのもひとつの方法です。納税期日を過ぎてしまった場合は、延滞日数に応じた延滞税が発生してしまいます。
給与所得以外の所得や2,000万円以上の所得がある、2ヵ所以上から給与の支給を受けているなど、一定の条件に該当する従業員に関しては確定申告が必要になるため、年末調整の際には注意しましょう。



労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな担当者の方には、人事労務から勤怠管理までが一つになったシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
-
勤怠データをワンクリックで取り込めるため、勤怠の締めから給与計算までをスムーズに自動化できる
-
昇格や異動に伴う給与体系の変更も、人事情報と連携しているため設定漏れを防ぐことができる
-
Web給与明細で印刷・封入コストがゼロ・ 発行ボタン一つで、全従業員へ給与明細を配布可能
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
所得税の関連記事
-


所得税の累進課税制度とは?年収別の計算事例や税負担軽減のポイントを紹介
勤怠・給与計算公開日:2022.04.18更新日:2025.12.19
-


所得税における通勤手当の課税・非課税ルールとは?交通費のとの違いも解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.27更新日:2025.05.20
-


所得税率の種類一覧|給与や賞与の所得税の計算方法も解説
勤怠・給与計算公開日:2022.03.24更新日:2025.12.19





















